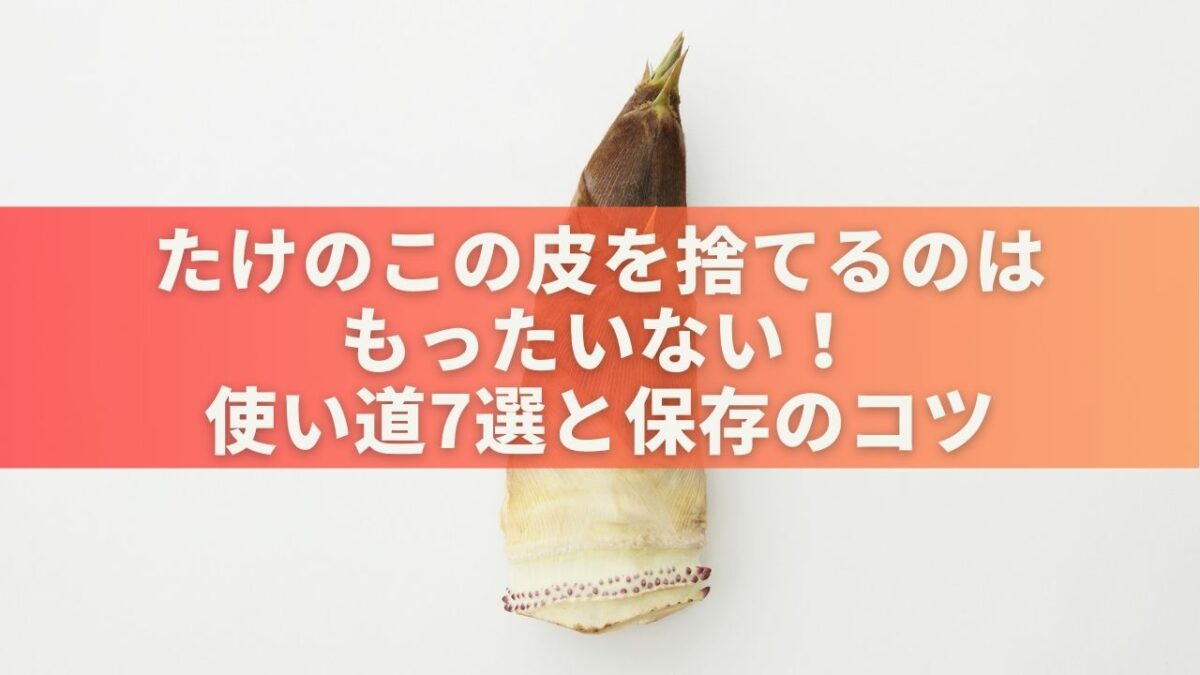たけのこを調理すると、たくさんの皮が剥がれますよね。
「この皮、何かに使えないかな?」と思ったことはありませんか?
実は、たけのこの皮にはさまざまな活用法があり、料理や掃除、保存の工夫次第で暮らしに役立てることができます。
この記事では、たけのこの皮の使い道を7つご紹介し、無駄なく活用する方法をお伝えします。
さらに、正しい保存方法も解説するので、すぐに使わない場合でも長く活かせますよ。
捨てる前に、ぜひチェックしてみてください!
たけのこの皮ってどんなもの?活用前に知っておこう

実は、たけのこの皮には外側と内側で異なる特徴があり、それぞれに適した使い道があります。
まずは、どの部分がどんな用途に向いているのかを整理してみましょう。
たけのこの皮の種類と特徴
| 皮の種類 | 特徴 | 活用法の例 |
|---|---|---|
| 硬い外皮(外側の茶色い皮) | 厚みがあり、繊維がしっかりしている | 出汁をとる、掃除や消臭に使う |
| 柔らかい姫皮(内側の白っぽい皮) | 薄くて柔らかく、なめらかな食感 | 食用として活用されることがあり、和え物・天ぷら・佃煮などに使われることがある |
※姫皮を食用にする際は、十分に加熱し、自己判断でお試しください。
硬い外皮(外側の茶色い皮)
特徴
- たけのこの一番外側にある、厚みのある皮
- 繊維が多く、ゴワゴワしていて硬い
- 水を含むと少ししなやかになる
この部分は食べることはできませんが、出汁をとったり、掃除や消臭などに活用できます。
具体的な活用方法については、このあと詳しく紹介しますね。
柔らかい姫皮(内側の白っぽい皮)
特徴
- 外皮を何枚か剥くと出てくる、白くて柔らかい部分
- しっとりとしていて、なめらかな食感
- ほのかな甘みがあり、食材として活用されることがある
この姫皮は、たけのこの中でも特に柔らかい部分とされています。
昔から、和え物や天ぷら、佃煮などに活用されることがあり、料理に使われることもあります。
食用にする場合は、十分に加熱し、自己判断でお試しください。
たけのこの皮はどこまで剥く?下処理の基本
でも、「どこまで剥けばいいの?」と迷うこともありますよね。
詳しい剥き方や下処理の方法については、こちらの記事で解説しています。
➡ たけのこの皮は剥いてから茹でる?どこまでむくの?茹で方の簡単な方法
たけのこを美味しく調理するために、ぜひ参考にしてみてください。
たけのこの皮の使い道7選【活用アイデア】

たけのこの皮は、ただ捨ててしまうだけではもったいない存在です。
実は、料理や暮らしの中で役立つ使い道がたくさんあります。
ここでは、たけのこの皮を活用する方法を7つご紹介します。
手軽にできるものばかりなので、ぜひ試してみてくださいね。
なお、たけのこの皮の活用法は、昔から伝えられている一般的な知恵のひとつです。
使用する際は、ご自身の判断でお試しください。
① 風味を引き出す!焼きたけのこの包み焼き
たけのこの皮は、天然のホイルのような役割を果たします。
皮ごと焼くことで、香ばしさが増し、うまみもギュッと閉じ込められます。
作り方
- 外側の硬い皮を2~3枚残し、たけのこを包む
- そのまま魚焼きグリル、オーブン、または炭火で20~30分ほど焼く
- 焼き上がったら皮をむき、塩や醤油をつけて食べる
実践しやすいポイント
- 皮は何枚残せばいい?
→ 外側の硬い皮を2~3枚残すと、焦げにくく、香ばしさもアップします。 - 火加減や時間の目安は?
→ グリルなら中火で20分、炭火なら30分が目安です。
② 香りを活かす!たけのこの皮で出汁をとる
たけのこの皮には、ほんのりとした竹の香りが残っています。
これを利用して、やさしい味わいの出汁をとることができます。
使い方
- たけのこの皮を鍋に入れ、水と一緒に10~15分ほど煮出す
- できた出汁を味噌汁や煮物のベースとして使う
実践しやすいポイント
- 皮はどのくらい入れる?
→ 鍋に5~6枚の皮を入れると、ほんのりとした風味がつきます。 - 他の出汁と合わせてもOK?
→ かつお節や昆布と一緒に使うと、より深みのある味わいになります。
③ まな板を汚さない!調理の下敷きに使う
魚や肉を切ると、まな板の汚れやニオイが気になりますよね。
そんなとき、たけのこの皮を敷いておくと、汚れがつきにくくなります。
使い方
- まな板の上にたけのこの皮を敷き、その上で魚や肉を切る
- 野菜の皮むきをするときの下敷きにも使える
実践しやすいポイント
- どの皮を使うと便利?
→ 内側がなめらかな皮の方が、食材が滑りにくく扱いやすいです。
④ エコで便利!お皿や食品包装として活用
たけのこの皮は適度な大きさがあり、お皿代わりにもなります。
特に、アウトドアやキャンプでは大活躍します。
活用例
- 焼いた魚や肉を盛り付ける
- おにぎりやおかずを包む
食品を包むときのポイント
乾燥しやすい食材を包む場合は、たけのこの皮を軽く湿らせてから使うと、適度な湿度を保つことができます。
⑤ 自然の力でピカピカに!フローリングのツヤ出し
たけのこの皮の内側はツルツルしており、軽いホコリや汚れを拭き取るのに使われることがあります。
昔からフローリング磨きに活用されることがあり、優しく拭くことで自然なツヤが出ることもあるようです。
実践しやすいポイント
-
どのように使えばいい?
→ たけのこの皮の内側はツルツルしているため、乾燥させたものを軽く当てるとホコリを拭き取りやすいと言われています。 -
より使いやすくするには?
→ 乾燥した皮を使うと、扱いやすく感じることがあるようです。湿らせると逆に繊維がほぐれやすくなるため、乾燥した状態で使うのがおすすめです。 -
注意点は?
→ 強くこすると細かい傷がつく可能性があるため、やさしく拭くことが大切です。
⑥ 消臭&湿気対策!靴や収納のニオイ取りに
乾燥させたたけのこの皮は水分を吸収しやすく、湿気対策として使われることがあります。
また、竹製品には消臭効果が期待されるものもあり、たけのこの皮も靴や収納のニオイ対策に役立つとされています。
実践しやすいポイント
- どのように使えばいい?
→ 乾燥させたたけのこの皮を小さめにカットし、ガーゼや布袋に入れて靴や収納に入れると使いやすいと言われています。 - どのくらいの期間で交換する?
→ 1~2週間ごとに天日干しすると、乾燥状態を保ちやすくなります。 湿気が多い時期は、こまめにチェックして入れ替えるのがおすすめです。 - より効果的に使うには?
→ 重曹と一緒に入れると、ニオイ対策として試されることがあります。 - 使えない場所はある?
→ 湿気を含んだまま密閉空間に入れると、カビが発生する可能性があるため、しっかり乾燥させてから使うことが大切です。
⑦ 最後まで無駄なく!堆肥(コンポスト)にする
たけのこの皮は天然素材なので、土に還ります。
生ごみとして処理すれば、堆肥(コンポスト)として再利用できます。
分解を早めるコツ
他の生ごみと一緒にすると、よりスムーズに分解されることがあります。
たけのこの皮の保存方法【長く活用するコツ】
「たけのこの皮をすぐに使わないけれど、何かに活用したい」という場合、正しい保存方法を知っておくと便利です。
保存期間に応じて、適切な方法で保管しましょう。
たけのこの皮の正しい保存方法
| 保存期間 | 方法 | 失敗しないポイント |
|---|---|---|
| 短期間(数日) | 乾燥を防ぐため、軽く湿らせた新聞紙に包み、ポリ袋に入れて冷蔵保存 | 新聞紙に包まずに保存すると乾燥しやすい |
| 長期間(数週間~数カ月) | しっかり乾燥させて密閉容器で保存(掃除や消臭用に使う場合) | 湿ったまま密閉するとカビが生えることがある |
カビを防ぐためのポイント
長期間保存する場合は、できるだけ湿気を避け、しっかり乾燥させることが大切です。
乾燥させる方法
- たけのこの皮を広げ、風通しの良い場所で天日干しする
- 1~2日ほど乾燥させ、パリッと折れるくらいになればOK
- 完全に乾燥したら、湿気の少ない場所で密閉保存する
ただし、乾燥させても湿度の高い環境ではカビが発生することがあります。
長期間保存する場合は、湿気がこもらないよう、保管場所にも注意しましょう。
まとめ|たけのこの皮を捨てずに賢く活用しよう!
たけのこの皮は、料理や掃除など、さまざまな場面で活用できます。
〈主な活用法〉
- 硬い外皮(茶色い皮) → 出汁をとる、掃除や消臭に使う
- 柔らかい姫皮(白っぽい皮) → 和え物・天ぷら・佃煮などに使われることがある
また、保存方法を工夫すれば、活用の幅を広げることができます。
- 短期間保存 → 新聞紙に包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫で保管すると乾燥を防げる
- 長期間保存 → 天日干しでしっかり乾燥させ、湿気の少ない場所で密閉保存する。ただし、保存環境によってはカビが生えることがあるため注意が必要。
たけのこの皮を無駄なく活用し、日々の暮らしに役立ててみてくださいね。
ところで、たけのこはどのサイズを選んでいますか?
小さいものと大きいもの、それぞれに違った特徴があり、向いている料理も異なります。
せっかくなら、料理に合ったサイズのたけのこを選んで、もっと美味しく楽しみませんか?
➡ たけのこは小さいのと大きいの、どっちが美味しい?特徴と選び方を徹底比較
こちらの記事では、たけのこの選び方のポイントを詳しく解説しています!
「どっちを選べばいいの?」と迷ったときの参考にしてくださいね。