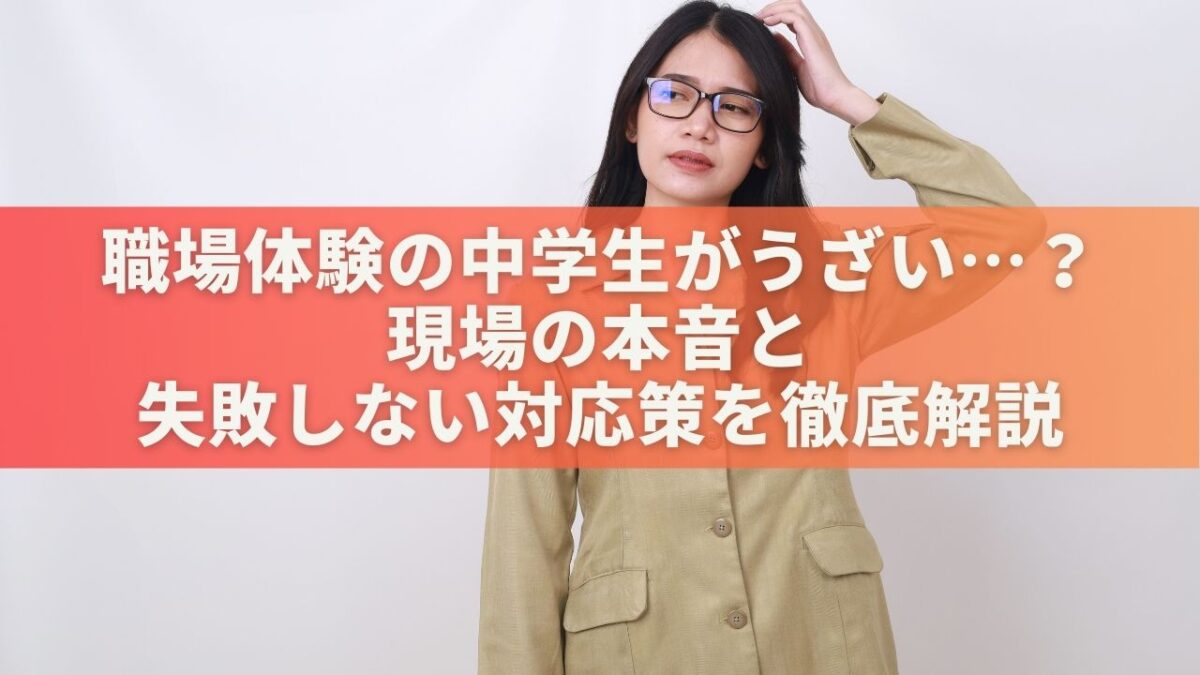「職場体験に来た中学生、正直ちょっと扱いづらい…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
- 指示しても動かない
- 雰囲気を読まずに話し出す
- こちらの仕事が止まってしまう…
「うざい」と感じてしまうのも無理はありません。
でもそれ、もしかしたら中学生側の“やる気のなさ”ではなく、ただ社会に不慣れなだけなのかもしれません。
この記事では、職場体験でよくある「受け入れ側のモヤモヤ」や「トラブルの原因」を整理しながら、中学生との関わりをスムーズにするための実践的な工夫や声かけのコツをご紹介します。
職場にとっても中学生にとっても、職場体験が“いい時間”になるように。
ちょっとしたヒント、ここから見つけてみませんか?
職場体験の中学生が「うざい」と感じるのはなぜ?
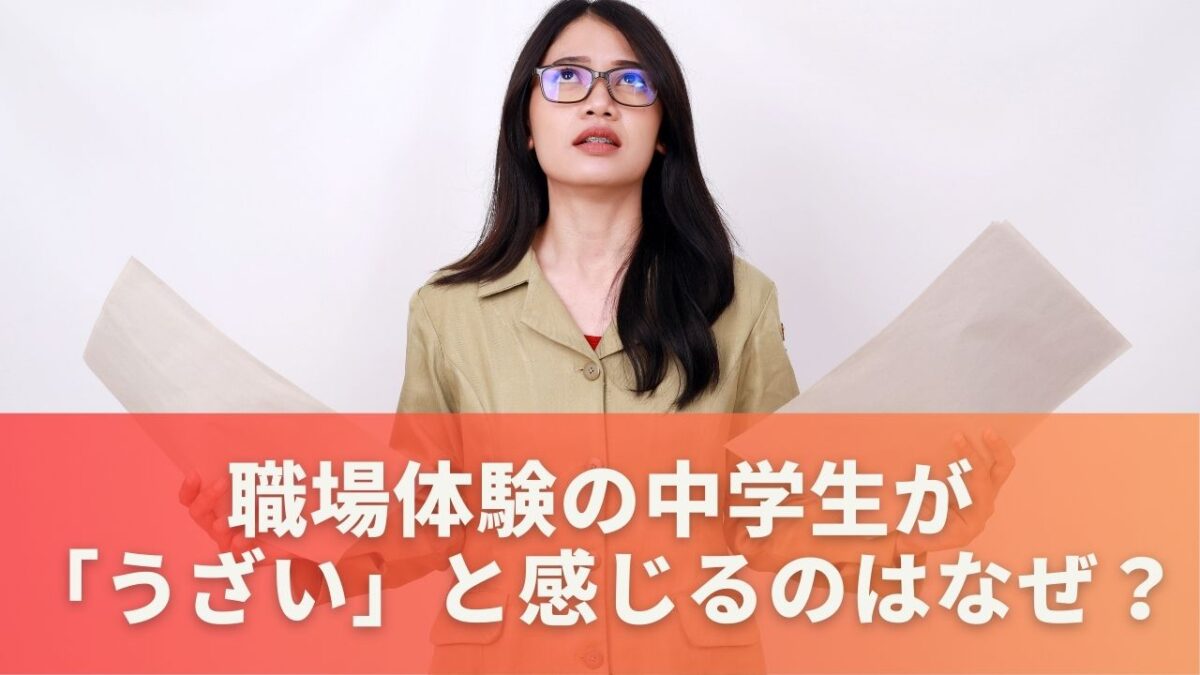
職場体験に来る中学生の多くは、これが初めての「働く場」への参加です。
当然ながら、社会人としての経験や仕事の常識が身についているわけではありません。
そのため、職場側が「こうしてほしい」と思っている行動をとれなかったり、逆に場にそぐわない振る舞いをしてしまったりすることがあります。
しかし、これは決して中学生が「ふざけている」「やる気がない」というわけではなく、単純に何をすればいいのかわからないだけなのです。
では、職場でよく見られる「行動のズレ」の具体例を見ていきましょう。
社会経験の少なさが引き起こす行動のギャップ
中学生は、まだ義務教育の最中。
社会に出た経験がまったくない状態で職場にやってきます。
そのため、企業や店舗が「常識」としているルールやマナーが、中学生にはわからないのです。
たとえば…
- 靴をそろえる、机をきれいに保つなどの基本的な所作
- あいさつの声が小さい、無表情で返事がない
- 「暇そうに立っている」ように見えてしまう態度
職場にとっては“当たり前”でも、中学生にとっては“はじめて”。
そのギャップがストレスを生む要因になります。
職場の忙しさと中学生のペースが合わない
現場が忙しい中で、右も左も分からない中学生がいると、どうしても「手間が増える」「自分の業務が進まない」と感じがちです。
中学生は「役に立ちたい」と思っていても、空回りしたり、何をしていいか分からず動けなかったりするもの。
そうした様子が「うざい」と感じられてしまうのです。
職場体験で起こりがちなトラブルとその原因

職場体験では、意図せずトラブルが発生することがあります。
職場側にとっては「当然のこと」でも、中学生にとっては初めての環境。
社会経験の少なさや認識の違いが原因で、思わぬ問題が起こることがあります。
次に、現場でよくあるトラブル事例とその背景を見ていきましょう。
中学生の職場体験でよくある問題と失敗事例
現場では、次のようなトラブルが頻繁に発生します。
| トラブル内容 | 背景・原因 |
|---|---|
| 作業ミス | 指示を正確に理解できていない。聞き返す勇気がない。 |
| スマホの使用 | 「休憩中ならOKと思った」「使ってはいけないと聞いていない」など、認識の違い |
| 無表情・無反応 | 緊張して声が出ない。返事の仕方がわからない。 |
| 私語やふざけた行動 | 気を緩めてしまう、他の中学生との距離が近すぎる |
一見すると「やる気がない」「常識がない」と感じられる行動も、背景には“経験のなさ”や“説明不足”があることが多いのです。
注意するだけでは解決しない?根本的な理解を促すポイント
ただ注意するだけでは、問題の本質は改善しません。
「なぜそれがダメなのか」「職場ではどう振る舞うべきか」を丁寧に伝えることで、納得し、自ら行動を変えるきっかけになります。
職場体験をスムーズにするための準備と対応策
「職場体験を受け入れたけど、正直疲れた…」という声の多くは、準備不足が原因です。
事前にしっかり準備をすることで、お互いにとってストレスの少ない体験になります。
① 受け入れ前にルールとマナーをしっかり共有する
中学生にとって職場体験は初めての“社会の現場”。
こちらが「当たり前」と思っていることも、知らないケースがほとんどです。
そのため、事前にルールとマナーを明文化し、初日にしっかり伝えることがとても重要です。
中学生に伝えるべき基本ルールの例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | ○時までに到着、遅れるときは必ず連絡 |
| 服装 | 制服/動きやすい服装などの指定があれば明示 |
| スマホ | 原則使用不可。緊急時以外はカバンに入れておく |
| 私語・態度 | 敬語を使う、ふざけない、挨拶をきちんとする |
| 飲食 | 所定の場所・時間以外はNG、などの明確なルール化 |
紙やスライドで“見える化”して渡すと、中学生の理解度がグッと上がります。
さらに、保護者や学校とも共有できるような資料にしておくとトラブル防止にもなります。
② 指示を明確に!やることリストを事前に用意しておく
当日、その場で「何を頼もうかな…」と考えていると、指示が曖昧になってしまい、結果的に中学生が手持ち無沙汰になります。
これは受け入れる側にも、教わる側にもストレスです。
そこでおすすめなのが、あらかじめ“やってもらう仕事”をリスト化しておくこと。
中学生向け「やることリスト」の例
| 作業内容 | 難易度 | ポイント |
|---|---|---|
| 書類の仕分け・整理 | ★☆☆ | 一人でできる簡単作業。達成感あり。 |
| 備品の補充・整頓 | ★☆☆ | 環境を整える大切な仕事。職場の意義を学べる。 |
| イベント準備 | ★★☆ | チームで協力しながら進める体験に。 |
| 掃除・片付け | ★☆☆ | 周囲の人に感謝される成功体験に。 |
こうしたリストがあると、中学生に「任せられている感覚」を与えることができ、自信とやる気につながります。
また、タスクごとに担当者を決めておくと、指導もスムーズになります。
③ 担当者を決めて「誰に聞けばいいか」を明確にする
「誰が見てあげるのか」が曖昧だと、現場も中学生も混乱しやすくなります。
特に中学生にとっては、「誰に何を聞けばいいのかわからない」ことが、大きな不安につながります。
そこで活用したいのが、以下のような担当割りルールの見える化です。
担当者の明確化イメージ(例)
| 時間帯・場面 | 担当スタッフ | 中学生への伝え方 |
|---|---|---|
| 午前(受付・見学) | 鈴木さん | 「何かあったら鈴木さんに聞いてね」 |
| 午後(清掃作業) | 山田さん | 「午後は山田さんの指示を聞いて動いてください」 |
| その他(全体) | チーム全員 | 「困ったら誰でも声かけて大丈夫」 |
こうした割り振りを表やホワイトボードにまとめておくだけで、中学生の動きが格段にスムーズになります。
④ 質問しやすい環境を作り、中学生の不安を解消する
中学生が自分から質問できない理由は、「怒られたくない」「迷惑をかけたくない」という不安から来ています。
だからこそ、最初の声かけで“安心できる空気”を作ることが大切です。
質問しやすい職場 vs しにくい職場
| 質問しやすい職場 | 質問しにくい職場 |
|---|---|
| 「困ったら何でも聞いてね」の声かけ | 無言で作業、話しかけづらい雰囲気 |
| 担当者が決まっていて、誰に聞けばいいか明確 | 役割が曖昧で、指示系統が不明 |
| 質問に対して「ありがとう」と返す | 「なんでそんなこと聞くの?」という空気 |
中学生には「質問=迷惑」ではなく、「質問=信頼の第一歩」と思ってもらえる対応が大切です。
⑤ ダレないスケジュール設計で職場体験を充実させる
集中力や体力が大人よりも劣る中学生にとって、単調な1日ではモチベーションが続きません。
午前・午後のメリハリある構成を意識するだけで、体験の質がぐっと上がります。
職場体験当日のおすすめスケジュール
【午前】
🔹 オリエンテーション
🔹 職場見学
🔹 簡単な作業体験
⬇
【昼休憩】
⬇
【午後】
🔸 実作業(清掃や準備)
🔸 振り返り・感想記入
担当者からのアドバイス・メッセージ
このように「見る→やる→ふり返る」のサイクルを意識することで、体験が単なる作業ではなく「学び」になります。
職場体験を受け入れるメリットとは?
「面倒だな…」という気持ちが先に立つこともあるかもしれません。
でも実は、職場体験の受け入れには、企業や現場にとっても思わぬメリットがあるんです。
① 業務の可視化が進み、職場の仕組みを見直せる
中学生に仕事内容を説明するには、業務の目的や流れをわかりやすく言語化する必要があります。
これが結果的に、「自分たちの仕事をどう整理すれば効率が上がるか」を見直すきっかけになります。
- 手順の無駄に気づけた
- 担当ごとの役割が曖昧だったことに気づいた
- 「新人にもこの説明が使える」と発見があった
など、内側に目を向けるチャンスにもなるんです。
② 育成スキルが向上し、新人教育にも役立つ
中学生はまだ社会の基本も知らない“超初心者”。
だからこそ、伝え方・反応の仕方・失敗への対応力が試されます。
これはまさに、
- 新人社員
- アルバイト
- 業界未経験者
への教育場面と同じ!
「どう説明すれば伝わるか」を考える経験が、育成スキルを自然と高めてくれます。
③ 中学生の存在が職場の雰囲気を明るくする
中学生が来るだけで、職場にちょっとした非日常感が生まれます。
普段の業務の中に会話が増えたり、同僚同士でも自然と笑顔がこぼれたり。
ときには「自分も中学生の頃、こうだったなあ」といった初心を思い出す機会にも。
実際に「職場がちょっと明るくなった」「良い気分転換になった」といった声も多く、メンタル的なリフレッシュ効果もあるのが意外なメリットです。
中学生に伝わる指導法と接し方のコツ
「教える側」としての関わり方ひとつで、中学生の態度や学びの深さは大きく変わります。
特に、失敗への向き合い方と、成功の見つけ方がポイントです。
ミスを責めず、「どうすればよかったか」を一緒に考える
中学生が職場で失敗するのは、ほとんどが“経験不足”によるもの。
怒られると萎縮してしまい、次にチャレンジできなくなってしまいます。
大切なのは、責めるのではなく、「次はどうする?」を一緒に考える姿勢です。
たとえばこんな声かけが効果的:
- 「この場面、どうしたらよかったと思う?」
- 「原因は何だったと思う?次に活かそう!」
- 「大丈夫、次がチャンスだからね」
“教える”ではなく、“育てる”という意識がカギです。
小さな成長を見逃さず、褒めるポイントを作る
中学生は、ちょっとしたことで不安にもなるけれど、ちょっとしたことで自信も持てる存在です。
ほんの些細なことでも、ポジティブなフィードバックをもらうと「見てくれているんだ」と感じて、意識と行動が変わります。
たとえば:
- 「さっきの挨拶、しっかりできてたね!」
- 「気づいて動いてくれて助かったよ」
- 「整理の仕方、すごくきれいだった!」
「できて当たり前」と見過ごさず、“気づき”を言葉にして伝えることが大切です。
職場体験でよくある悩みとその解決策【Q&A】
中学生を受け入れる職場体験は、意義のある取り組みである一方で、実際の現場ではさまざまな“本音の悩み”もあるのが事実です。
ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめ、無理なく・前向きに受け入れるためのヒントをご紹介します。
Q:本音では業務の邪魔になると感じている…対策は?
→ 業務負担が増えること自体は、ごく自然なことです。
だからこそ、受け入れ方に工夫をしましょう。
- 半日同行制にして、負担を分散する
- 業務ごとに担当を交代し、個人の負担を減らす
- 忙しい時間帯は見学メインにする など
「できる範囲で受け入れる」ことが、長く続けられるコツです。
Q:どこまで注意すべき?叱り方のベストバランス
→ 注意が必要な場面では、遠慮せず伝えてOKです。
ただし、感情的にならず、「なぜそれが大事なのか」を説明するのがポイント。
- 例)「時間を守るのは、みんなの信頼につながるからね」
- 例)「今は作業中だから、話すのは休憩時間にしよう」
“正す”だけでなく、“育てる”視点で言葉を選ぶことが大切です。
Q:やる気のない生徒が来たらどう対応すればいい?
→ 一見やる気がなさそうに見えても、「興味のスイッチ」が入っていないだけということも多いです。
まずは、「あなたに任せたい仕事がある」「これ、お願いできるかな?」と声をかけて、期待されている実感を持たせましょう。
場合によっては、簡単な成功体験を通して、意識が大きく変わることもあります。
まとめ|「うざい」の裏には、成長のきっかけがある
職場体験の中学生に対して、「うざいな…」「ちょっと扱いづらいな…」と感じてしまうのは、決して特別なことではありません。
でも、その背景には、社会を知らない不安・経験の少なさ・うまく動けない戸惑いがあるだけなのかもしれません。
受け入れる側のちょっとした工夫と声かけで、中学生の態度も、表情も、学ぶ姿勢も大きく変わります。
そして実は、教える側である職場にも――
- 自分たちの仕事を見直すきっかけ
- 育成力や伝える力を磨く機会
- チームの空気をやわらかくする小さな変化
そんな思いがけない“ギフト”が返ってくることもあるのです。
職場体験は、単なるイベントではなく、未来の社会人と、今の現場をつなぐ“学び合い”の場。
「ちょっと面倒…」を、「ちょっと良い経験かも」に変えるのは、ほんの一言、ほんのひと工夫から、始まります。
職場体験は、一方通行ではなく「お互いに学び合える場」。
実は中学生のほうも、「うざいって思われたらどうしよう…」と不安を感じていることが多いのです。
そんな中学生に向けて、“どうすれば好印象を残せるか”をまとめた記事を紹介します。
➡ 職場体験で『うざい』と思われたくない中学生へ!好印象を残す行動&マナー
よければ、事前にシェアしてあげてください。
きっと、職場体験がもっと前向きな時間になるはずです。