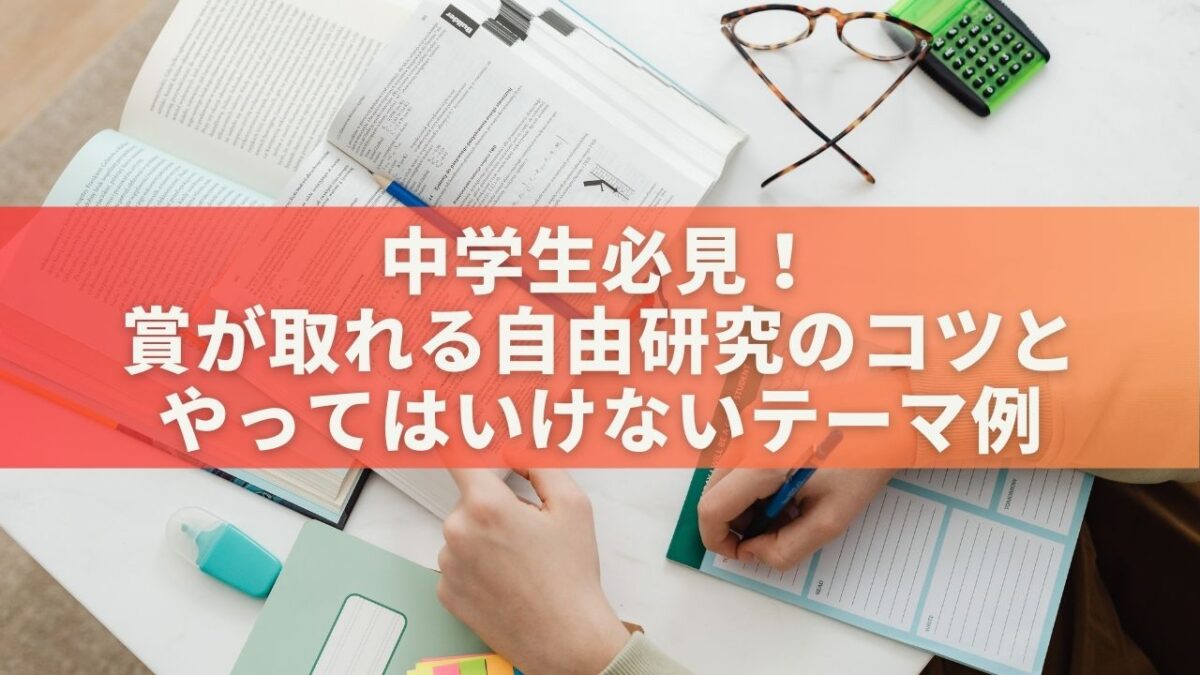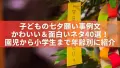「せっかく自由研究をするなら、賞を狙いたい!」
そう思ったことはありませんか?
自由研究は、夏休みの宿題の中でも時間がかかる大きな課題です。
どうせやるなら、「これはすごい!」と評価される研究にしたいですよね。
でも、「どんな研究が評価されやすいの?」「やってはいけないテーマってあるの?」そんな疑問を持っている人も多いはず。
実は、入賞しやすい自由研究には共通するポイントがあります。
この記事では、賞を取るためのコツと、選んではいけないテーマの例をわかりやすく解説します!
最後まで読めば、自由研究で評価される秘訣がきっとわかりますよ。
あなたの研究を「入賞レベル」に引き上げるヒントを、一緒に見ていきましょう!
賞が取れる自由研究のコツ5つ
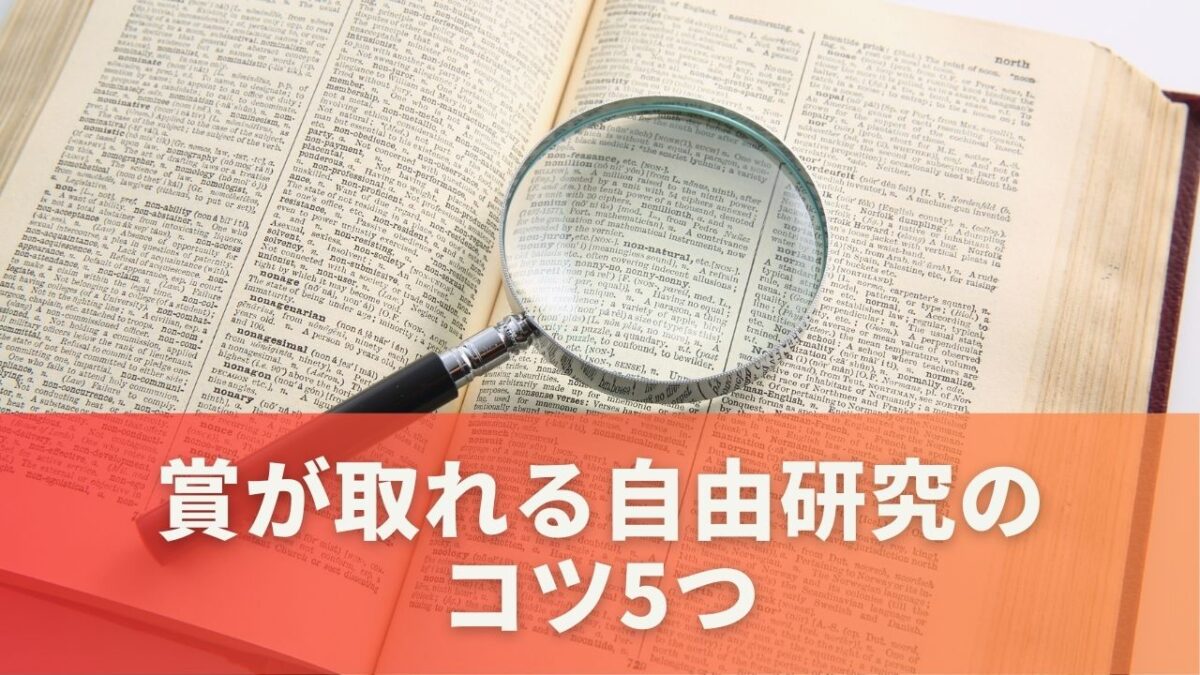
自由研究で賞を取るには、評価されやすい研究の特徴を知ることが大切です。
「どんな研究が入賞しやすいのか?」を理解し、ワンランク上の自由研究を目指しましょう!
時間をかけてじっくり研究する
1日で終わる自由研究より、長く続ける研究のほうが評価されやすいです。
長期間データを集めると、研究の内容が深まり、説得力が増すからです。
たとえば…
- 植物の成長を調べるなら1か月間観察する
- 水質の変化を調べるなら毎日データをとる
短期間の実験でも、条件を変えて比べるなどの工夫をすれば、より詳しい研究になります。
大人のアドバイスをうまく活用する
自由研究は「自分でやるもの」ですが、大人に相談すると、より良い研究になります。
こんなふうに聞いてみよう!
- 先生に研究の進め方を相談する
- 家族に実験の手伝いをお願いする
- 図書館や専門サイトで詳しい情報を調べる
ただし、大人に頼りすぎると「自分の研究ではない」と思われてしまいます。
アドバイスをもらいつつ、自分で考えて進めることが大切です。
教科書をヒントに研究の精度を上げる
自由研究のテーマに迷ったら、理科の教科書を見てみましょう。
教科書にはすでに科学的に証明されている情報がたくさんあり、研究のヒントになります。
たとえば…
- 「水はどうやって蒸発する?」→温度を変えて実験してみる
- 「植物の成長に光は必要?」→明るい場所と暗い場所で育てて比べる
教科書を使うと、「何を調べればいいのか」がわかり、研究の方向性が決まりやすくなります。
自由研究本をそのままマネしない
本屋には「自由研究のアイデア集」がたくさんありますが、そのままマネするだけでは、オリジナリティがなく、評価されにくいです。
ただし、使い方を工夫すればOK!
- 本に載っている実験を別の方法でも試してみる
- 本の内容をもとに新しい疑問を見つける
たとえば、本に「水のろ過実験」が載っていたとします。
そのままやるのではなく、「ろ過の時間を変えたらどうなる?」など、自分なりに工夫すると、独自性のある研究になります。
わかりやすく整理してまとめる
どんなに良い研究をしても、まとめ方がバラバラだと伝わりません。
「結果はどうだった?」「なぜこの実験をしたの?」がすぐにわかるようにしましょう。
おすすめの流れ
- テーマを決める(何を調べるのか?)
- 予想する(こうなるはず!と考える)
- 実験・観察をする(データを集める)
- 結果をまとめる(何がわかったか?)
- 考察する(どうしてこの結果になったのか?)
さらに、写真・グラフ・表を使うと、より見やすくなります。
研究の質を高める工夫を知る
賞を取る自由研究には、5つのポイントがあります。
- 長期間の研究をする(データを増やす工夫をする)
- 大人の意見もうまく活用する(相談しながら自分で考える)
- 理科の教科書を活用する(研究のヒントにする)
- 自由研究本をそのままマネしない(アレンジしてオリジナリティを出す)
- 研究の流れを整理する(伝わりやすくまとめる)
これらを意識すると、自由研究の完成度が上がり、入賞する可能性が高まります。
しっかり準備して、自分だけのオリジナル研究に挑戦してみましょう!
そんな中で、「賞を狙いたいけど、まわりと同じようなテーマにはしたくない…」と思っている人におすすめなのが、こちらの記事です。
➡ 【中学生向け】人とかぶらない自由研究40選!面白い&簡単なテーマや成功のコツ
面白い・簡単・化学・実験・社会・工作など幅広いテーマを紹介しているので、自分に合った研究テーマを見つけたい人にぴったり。
ほかの人とはちがう“自分らしさ”を取り入れてみましょう。
やってはいけない自由研究のテーマ
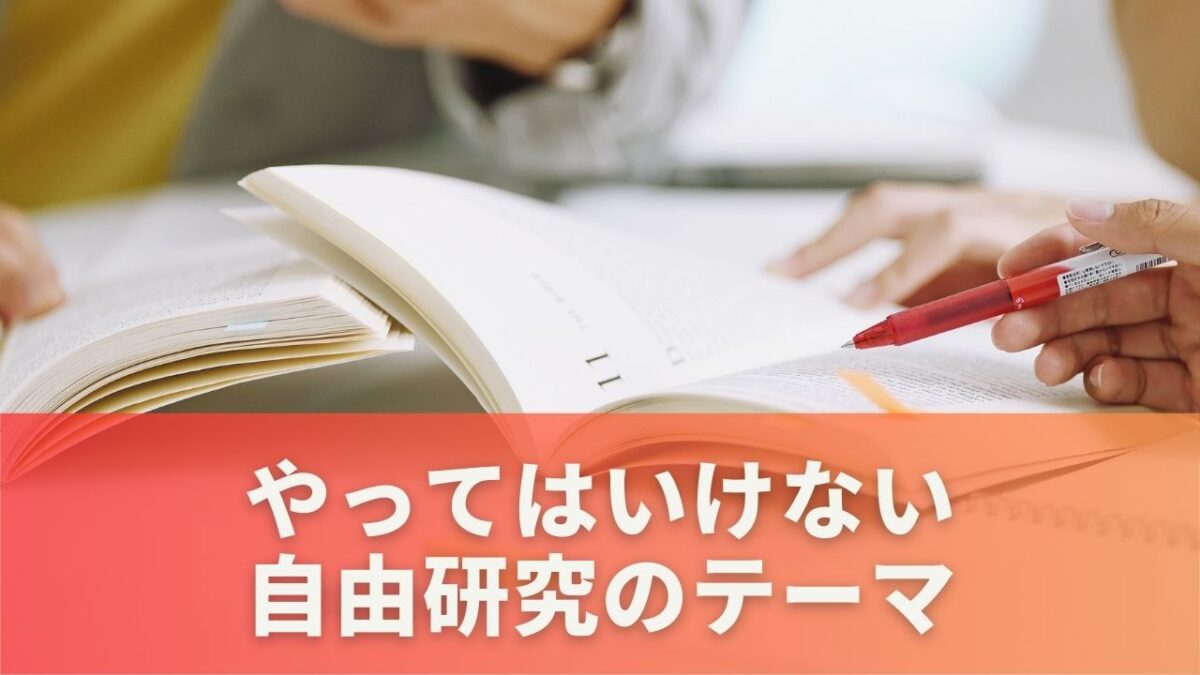
賞を狙うなら、「やらないほうがいい自由研究」 も知っておくことが大切です。
評価されにくいテーマを選んでしまうと、どんなに頑張っても入賞は難しくなります。
では、どんな自由研究が失敗しやすいのでしょうか?
| 失敗しやすいテーマ | 理由・問題点 |
|---|---|
| 準備が大変すぎる | 材料が手に入りにくい、時間がかかりすぎる |
| すぐに終わる実験 | データが少なく、深く考察できない |
| 結果がわかりきっている | すでに知られていることを確認するだけになる |
| 自由研究本をそのままマネする | オリジナリティがなく、評価されにくい |
準備が大変すぎる研究は避ける
自由研究には時間の限りがあります。
材料をそろえるのが難しい研究や、何週間もかかる実験は、途中でうまく進まなくなる可能性があります。
どうすればいい?
身近なものでできる研究を選ぶと、スムーズに進めやすくなります。
1日で終わる実験はデータ不足になりやすい
1日で終わる実験は、データが少なく、深い考察ができません。
データの量が少ないと、「なぜそうなるのか?」をしっかり考えにくいので、評価が低くなりやすいです。
どうすればいい?
同じ実験を何回もくり返したり、条件を変えて比べたりすると、内容が充実します。
結果がわかりきっている研究は新鮮味がない
「やる前から結果が決まっている実験」は、自由研究としての面白みが少なくなります。
すでに知られていることを確認するだけでは、「新しい発見」がないため、入賞は難しくなります。
どうすればいい?
少し工夫を加えて、「こうすると結果は変わる?」という視点を入れると、オリジナリティが出ます。
自由研究本の内容をそのままコピーしない
自由研究の本に載っているテーマをそのままやると、他の人と内容がかぶってしまうため、入賞しにくくなります。
本に書かれている内容はあくまで「ヒント」として使い、自分なりの工夫を加えることが大切です。
どうすればいい?
- 「ロケットの形を変えたら飛び方はどう変わる?」
- 「静電気をためる素材によって、発生の仕方は変わる?」
少しの工夫で、「自分だけの自由研究」になります。
失敗しやすいテーマの特徴を知る
やってはいけない自由研究のテーマには、共通する4つの特徴があります。
これらを避けて、「少し工夫を加える」ことが大切です。
オリジナリティのあるテーマを選べば、入賞の可能性がぐっと高まります!
自由研究をいつから始める?計画的に進める方法
自由研究は、できるだけ早く取り組むことが成功のカギです。
ギリギリになって焦ると、実験やまとめが雑になり、完成度が下がってしまうこともあります。
計画的に進めることで、余裕を持ってじっくり研究できます。
おすすめのスケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 夏休み開始前 or 1週目 | テーマ決め&情報収集 |
| 夏休み2週目〜3週目 | 実験・観察・データ収集 |
| 夏休み4週目 | まとめ・レポート作成 |
| 最後の1週間 | 見直し&仕上げ |
1週目:テーマを決めて情報を集める
まずは、どんな研究をするのかを決めることが大切です。
テーマを決めたら、本やインターネットを使って事前に情報を集めましょう。
この時期にやること
- 興味のあるテーマを考える(「なぜ?」と思ったことを探してみる)
- 調べる方法を決める(観察・実験・アンケートなど)
- 必要な材料や道具をリストアップ(すぐ手に入るものか確認)
2〜3週目:実験・観察を進める
この時期は、実際に研究を進める期間です。
植物の成長を観察する研究や、水質の変化を調べる研究など、時間がかかる実験は早めにスタートしましょう。
この時期にやること
- 計画通りに実験や観察を進める
- データを記録する(ノートに書いたり、写真を撮ったりするとわかりやすい)
- うまくいかなかった場合は、やり方を調整する
4週目:レポートをまとめる
実験や観察が終わったら、結果を整理してレポートを作成します。
データが多い場合は、表やグラフを使うと見やすくなるのでおすすめです。
この時期にやること
- 実験や観察の結果をまとめる
- 表やグラフを作る(データをわかりやすく整理)
- 考察を書く(「なぜこうなったのか?」を説明する)
最後の1週間:見直しと仕上げをする
完成したレポートを一度見直し、わかりやすく修正することが大切です。
また、発表がある場合は、説明の練習をしておくと安心です。
この時期にやること
- 誤字や内容のミスがないかチェック
- 図や写真を追加して、見やすくする
- 発表の準備をする(発表がある場合は、簡単な説明を考えておく)
スムーズに進めるためのスケジュールを立てる
自由研究を成功させるためには、計画的に進めることが重要です。
「いつ何をすればいいのか?」を決めておくと、スムーズに進めることができます。
- 夏休み開始前〜1週目:テーマ決め&情報収集
- 夏休み2〜3週目:実験・観察・データ収集
- 夏休み4週目:まとめ・レポート作成
- 最後の1週間:見直し&仕上げ
特に、植物の成長や水質の変化など、時間がかかる研究は早めにスタートすることが大切です。
しっかり準備して、完成度の高い自由研究を仕上げましょう!
わかりやすいレポートの書き方
自由研究のレポートは、「見やすく・わかりやすく」 まとめることが大切です。
しっかり整理されていると、研究の流れが伝わりやすくなり、評価も高くなります。
レポートの基本構成
- タイトル(研究のテーマ)
- 研究の目的(なぜこの研究をしようと思ったのか)
- 仮説(どんな結果になると予想したか)
- 方法(どのように実験・観察を行ったか)
- 結果(データやグラフを使って説明)
- 考察(結果からわかったこと、今後の課題)
- 感想(研究を通じて学んだこと)
タイトル(どんな研究をしたのか)
レポートの最初に、「何を研究したのか?」が一目でわかるタイトルをつけます。
シンプルで、研究内容が伝わるものにしましょう。
例:
- 「氷はどんな条件で早く溶ける?」
- 「植物の成長に光の強さは関係するのか?」
研究の目的(なぜこの研究をしようと思ったのか)
「なぜこのテーマを選んだのか?」を書きます。
自分の興味や、日常の疑問からスタートするとよいでしょう。
例:
- 「夏にアイスがすぐに溶けるのが気になったので、氷が溶ける速さを調べてみたいと思った。」
- 「家の植物の育ち方が違うので、光の当たり方が関係しているのか知りたいと思った。」
仮説(どうなると思ったか)
研究を始める前に、「こうなるはず!」と予想を立てます。
「なぜそう考えたのか?」の理由も書くと、より良いレポートになります。
例:
- 「温度が高い場所のほうが、氷は早く溶けると思う。」
- 「光が強いほうが、植物は大きく育つと予想した。」
方法(どんな実験や観察をしたか)
研究のやり方を、できるだけ詳しく書きます。
誰が読んでも同じ実験ができるようにするのがポイントです。
書くべきこと:
- 準備したもの(材料・道具)
- 実験の手順(何を、どのように調べたか)
- 実験や観察の期間(いつからいつまで?)
例:
- 「同じ大きさの氷を、室温20℃・30℃・40℃の部屋に置いて、溶ける時間を測った。」
- 「同じ種類の植物を、強い光・普通の光・暗い場所に置いて成長を観察した。」
結果(何がわかったか)
実験や観察でわかったことを、表やグラフを使って説明します。
書くべきこと:
- 実験や観察のデータ(数値・写真・グラフなど)
- どんな変化があったか
- 予想と合っていたか
例:
- 「40℃の部屋の氷が、一番早く溶けた。」
- 「暗い場所に置いた植物は、あまり成長しなかった。」
表やグラフを入れると、データが見やすくなります。
考察(なぜこの結果になったのか)
結果をもとに、「なぜこうなったのか?」を考えます。
書くべきこと:
- 結果の理由(なぜこの結果になったのか)
- 予想と違った場合、何が原因か
- 今後の課題(もっと詳しく調べるなら、どうするか)
例:
- 「氷が早く溶けたのは、温度が高いほど分子が活発に動くからだと考えられる。」
- 「植物の成長には光が必要だが、光が強すぎると成長に悪影響を与えるかもしれない。」
感想(やってみてどうだったか)
研究をしてみて、「どんなことに気づいたか?」を書きます。
苦労したことや、楽しかったことも入れると、良いレポートになります。
例:
- 「温度が高いほど氷が早く溶けることが、実験でよくわかった。」
- 「植物の成長には光が大切だとわかったが、水の量も影響するのでは?と新しい疑問が生まれた。」
伝わりやすいレポートを作るポイント
① 伝えたいことを簡潔に書く
長すぎる文章より、短くスッキリまとめると読みやすい。
② 表やグラフを入れる
データをわかりやすくするために、数字や変化をグラフで見せると◎
③ 見出しをつける
各項目ごとに太字の見出しをつけると、スムーズに読める。
自由研究のレポートは、「何を調べ、どうやって研究し、何がわかったか?」を整理してまとめることが大切です。
基本の構成
- タイトル(研究のテーマ)
- 研究の目的(なぜこの研究をしようと思ったのか)
- 仮説(どんな結果になると予想したか)
- 方法(どのように実験・観察を行ったか)
- 結果(データやグラフを使って説明)
- 考察(結果からわかったこと、今後の課題)
- 感想(研究を通じて学んだこと)
この流れでまとめると、研究の内容がしっかり伝わります。
表やグラフを使いながら、見やすく整理するのもポイントです。
しっかりまとめて、わかりやすいレポートを作りましょう!
写真や図を使ってわかりやすくまとめる
自由研究では、「見やすさ」も評価に大きく関わります。
どんなに良い研究でも、文字だけのレポートでは伝わりにくく、説得力が弱くなることがあります。
そこで大切なのが、写真や図を活用すること。
研究の流れや結果を視覚的にまとめることで、よりわかりやすく、読みやすいレポートになります。
写真や図を活用するポイント
① 観察記録には写真をつける
長期間の観察をする場合、写真を撮っておくと変化がわかりやすくなります。
特に、植物の成長・天気の変化・水の蒸発量など、時間とともに変化する研究には写真が有効です。
例:
- アサガオの成長を観察するなら、1日ごとの写真を並べて比較すると、成長の違いがよくわかる
- 雲の種類を調べるなら、数日間の空の写真を記録すると、変化が見えてくる
② 実験の手順をイラストや表で整理する
実験の流れを説明するとき、文字だけでは手順が伝わりにくくなることがあります。
イラストや表を使うと、何をどうやったのかが一目でわかるため、審査員にも伝わりやすくなります。
例:
- 「水のろ過実験」の説明では、ろ過の仕組みをイラストで描くと理解しやすい
- 「温度による氷の溶け方」の実験では、表にして整理すると比較が簡単
③ 結果をグラフにして整理する
数値データがある場合、表や文章だけでは変化や違いがわかりにくいことがあります。
そこで、折れ線グラフや棒グラフを使うと、結果がひと目でわかるようになります。
例:
- 植物の成長を記録した場合、「日ごとの高さ」を折れ線グラフにすると成長の傾向が見やすい
- 温度による氷の溶け方を調べた場合、「何度のときに何分で溶けたか」を棒グラフにすると比較しやすい
長期間の研究ほど、写真や図が大切
特に、「長い時間をかけて観察する研究」の場合は、写真や図があると研究の説得力がぐっと増します。
長期間の研究例:
- 植物の成長(発芽~開花までの様子を写真で記録)
- 天気の変化(毎日の空の写真を撮り、天気と気温の関係を調べる)
- 水の蒸発量(数日ごとに水の量を測り、変化をグラフで整理する)
「変化を記録する研究」では、日ごとに写真を撮ったり、データを表にまとめたりすると、より詳しく研究の成果を示すことができます。
文字ばかりにならないように工夫するコツ
写真や図をうまく使うことで、「読んでいて疲れないレポート」になります。
工夫のポイント:
- 長い文章が続かないように、適度に写真や表を入れる
- データの説明には表やグラフを使う(文章だけだと数値がわかりにくい)
- 見出しを使って、「どこに何が書いてあるか」をわかりやすくする
特に、「実験の流れ」「結果の比較」などは、図や表を活用すると見やすくなります。
実際に入賞した自由研究のテーマ
過去に賞を取った自由研究のテーマには、「独自の視点」「長期間の観察」「科学的な分析」 など、共通するポイントがあります。
ここでは、入賞しやすい自由研究のテーマと、それぞれの特徴を紹介します。
| 研究テーマ | ポイント |
|---|---|
| 果物や野菜の浮き沈み実験 | 水に浮くものと沈むものの違いを調べ、密度や表面の違いを考察する |
| 昆虫の生態研究(セミ・トンボなど) | 一種類の昆虫を長期間観察し、成長の過程や行動パターンを詳しく記録する |
| 植物の成長に影響を与える要素の研究 | 光・水・温度などの条件を変えて、植物の成長にどんな影響があるかを比較する |
| 確率・統計を使った研究 | 日常の現象(じゃんけんの勝率やサイコロの目など)を数学的に分析する |
| 料理の素材と味の関係を調査 | 材料の組み合わせや調理法の違いが、味や食感にどのように影響するかを実験する |
入賞しやすい研究の特徴
- 「なぜ?」という疑問を深く掘り下げている
- 実験・観察を長期間続け、データをたくさん集めている
- 結果を表やグラフにまとめ、分かりやすく整理している
- 日常の身近なものを科学的に分析している
たとえば、「果物や野菜の浮き沈み実験」では、単に水に入れて浮くか沈むかを確認するだけでなく、「なぜ沈むのか?なぜ浮くのか?」 を密度や空気の量と関連づけて考察することで、より評価されやすくなります。
過去の受賞作を知る方法
もし 「他の受賞作品を知りたい」 という場合は、以下のような方法で調べることができます。
① 科学コンテストや自由研究コンクールの公式サイトを確認する
各団体が開催するコンテストの過去の受賞作品が掲載されていることがあります。
- 学研 自由研究コンテスト
- 日本学生科学賞(JST主催)
- 全国児童才能開発コンテスト
② 学校や地方自治体の自由研究発表会の結果を調べる
地域ごとの科学展や自由研究発表会の入賞作品が、自治体のウェブサイトや学校の掲示で発表されることがあります。
③ 書籍や新聞記事を参考にする
自由研究に関する書籍では、「過去の入賞作品例」 が紹介されていることがあります。
また、新聞や教育関連サイトで、「今年の受賞作品」 が取り上げられることもあります。
まとめ
自由研究で賞を取るためには、「テーマ選び」「研究の進め方」「レポートのまとめ方」が重要です。
自由研究は、「計画的に進めること」と「自分ならではの工夫を加えること」が成功のカギです。
しっかり準備して、あなたらしいオリジナル研究に挑戦してみてください。
\中学生だからこそ、小学生の研究テーマがヒントになる!/
自由研究で「もっと人とかぶらないテーマを探したい」「身近なことから発展させたい」と感じたら、小学生向けの自由研究アイデア80選をぜひチェックしてみてください!
このまとめ記事では、1年生〜6年生までの学年別に、“簡単だけど発見がある”面白いテーマや、実験・観察・調査など多彩なアイデアを紹介しています。
中学生でも応用できるものや、研究の基礎に立ち返るヒントが見つかるかもしれません。
また、弟や妹の自由研究のアドバイスをしたいときにも、すぐに役立ちますよ!