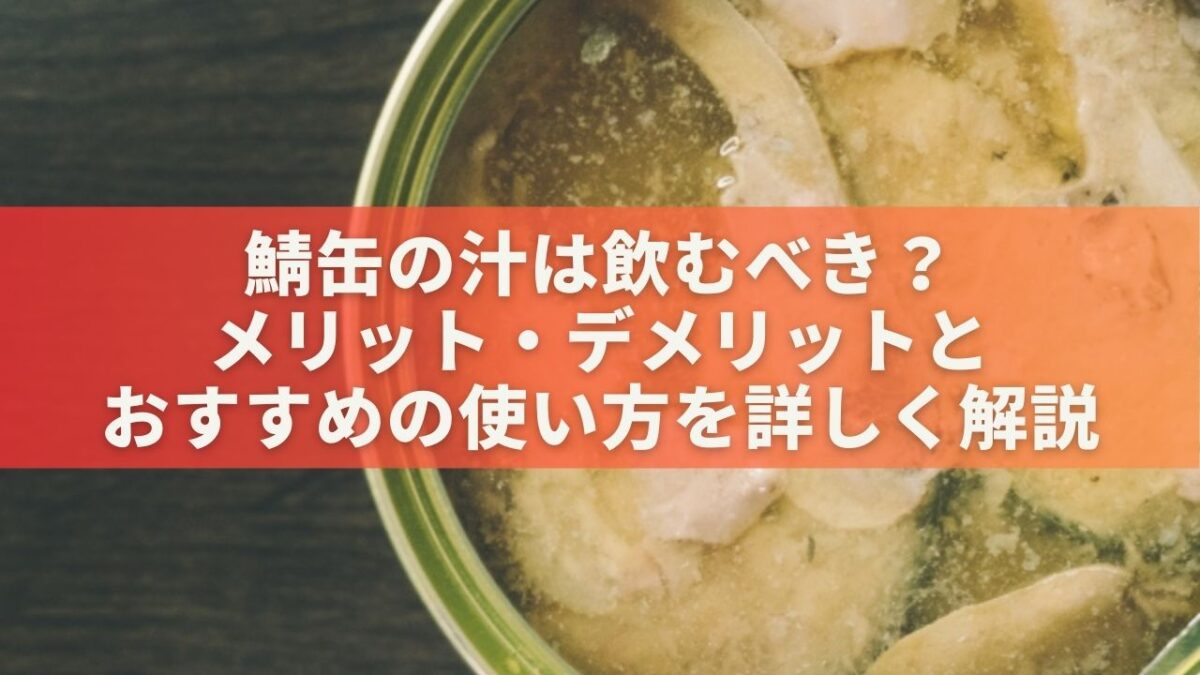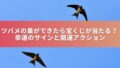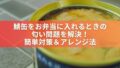「鯖缶の汁って飲んでも大丈夫?」
「栄養があるって聞くけど、塩分は気にならない?」
鯖缶を食べるとき、汁を飲むべきか捨てるべきか迷ったことはありませんか?
実は、鯖缶の汁にはDHA・EPAやビタミンB群などの栄養がたっぷり含まれています。
しかし、一方で塩分も多く、飲み方には工夫が必要です。
この記事では、鯖缶の汁を飲むメリット・デメリット、塩分対策、料理への活用法まで詳しく解説!
「捨てるのはもったいないけど、どう活用すればいい?」と気になっている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
鯖缶の汁には栄養がたっぷり!飲むべき理由とは?
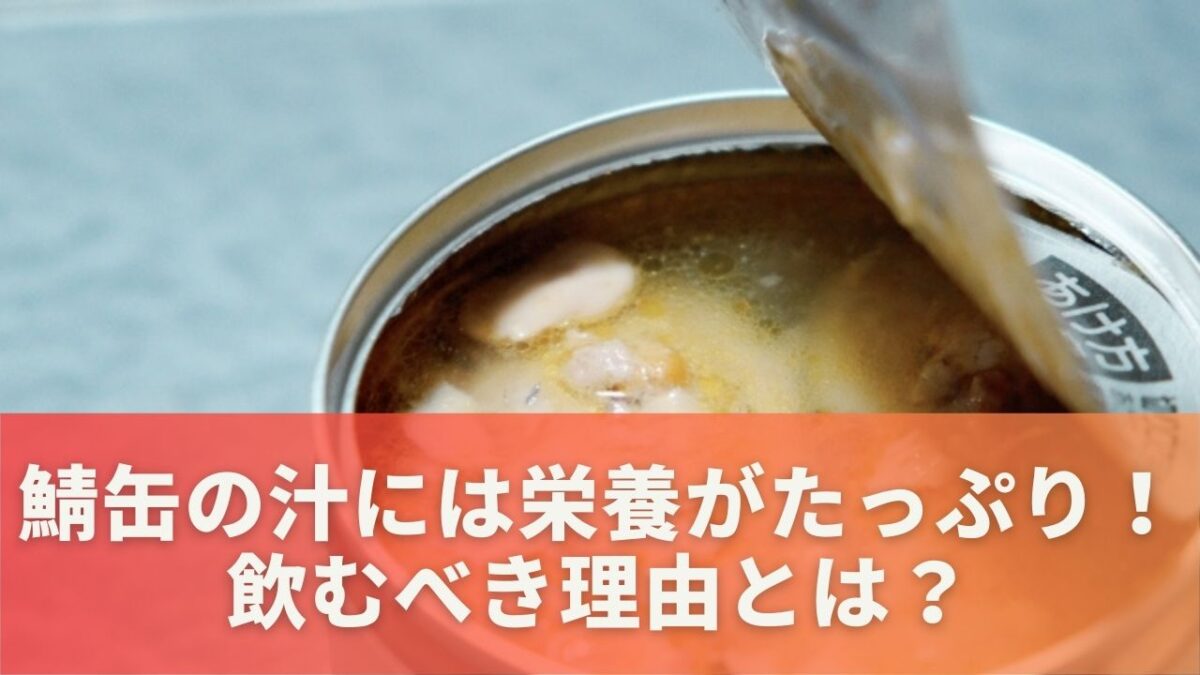
鯖缶は、生の鯖を缶に詰めてから高温加熱処理されるため、栄養が汁に溶け出しているのが特徴です。
特に注目したいのが、以下の栄養素です。
- DHA・EPA(血液をサラサラにする良質な脂質)
- ビタミンB群(代謝を助ける重要な栄養素)
- ミネラル(カルシウムやマグネシウムなど)
さらに、大手食品メーカーのマルハニチロの調査によると、鯖缶のDHA・EPAの約1~2割が汁に溶け込んでいるとのこと。
つまり、汁を捨ててしまうと、せっかくの栄養まで捨ててしまうことになります。
とはいえ、「そのまま飲むのはちょっと…」という方もいるはず。
後ほど、飲みやすくする方法や活用法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
鯖缶の汁は安全?そのまま飲んでも大丈夫?
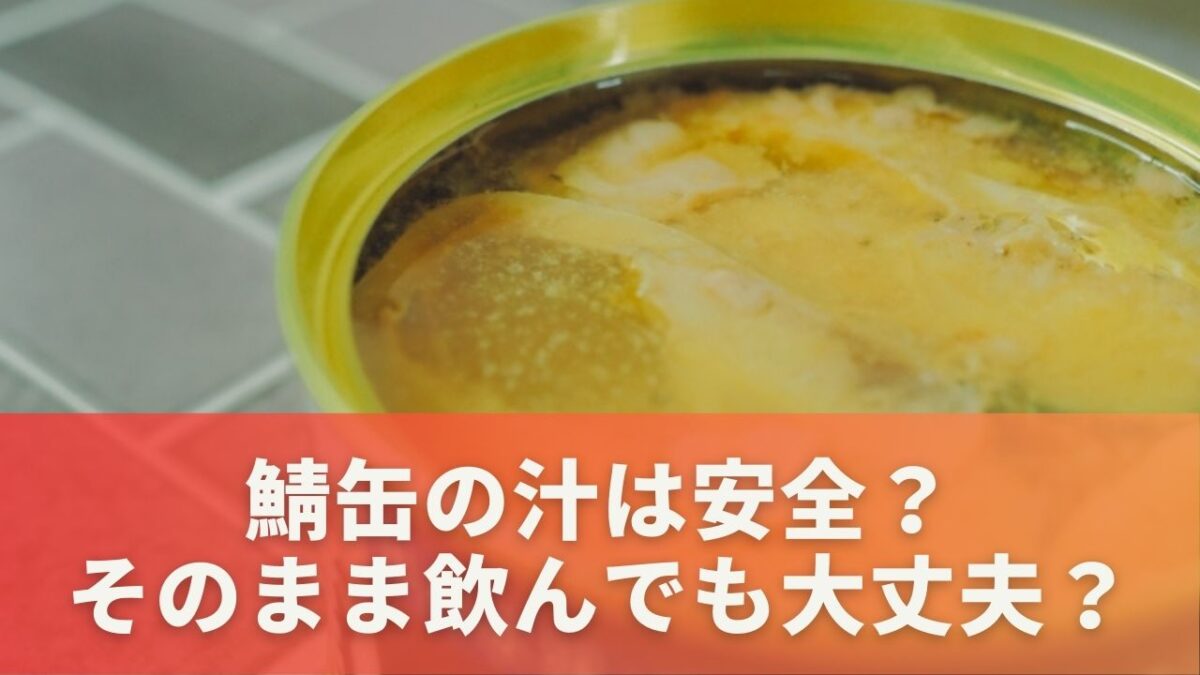
「鯖缶の汁って、そのまま飲んでも大丈夫?」と気になる方もいるかもしれません。
結論から言うと、鯖缶の汁は高温加熱処理されているため、適切に管理すれば安全に飲めると考えられます。
その理由は、缶詰は密閉された状態で加熱殺菌されており、適切に保存すれば雑菌の繁殖リスクは低いとされています。
ただし、注意点もあります。
- 開封後は早めに使い切る:鯖缶の汁は長時間放置すると酸化が進み、風味が落ちてしまいます。開封したらできるだけ早く使い切りましょう。
- 保存は冷蔵庫で:すぐに使わない場合は、密閉容器に移して冷蔵庫で保存し、1~2日以内に使い切るのがベスト。
- 常温放置はNG:開封後に常温で放置すると、雑菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。
そのまま飲むことも可能ですが、後ほど紹介する料理への活用法を試すと、より美味しく栄養を摂取できます!
鯖缶の汁を飲むメリット・デメリット
鯖缶の汁には栄養がたっぷり含まれているため、「飲むべきか迷う…」という方も多いのではないでしょうか?
実際、DHA・EPAやビタミンB群などの栄養素が溶け出しており、上手に活用すればメリットがたくさんあります。
しかし一方で、塩分が多いなどの注意点もあるため、飲み方には工夫が必要です。
ここでは、鯖缶の汁を飲むメリットとデメリットを分かりやすく解説 していきます!
鯖缶の汁を飲むメリット
鯖缶の汁には、栄養が豊富に含まれているだけでなく、さまざまなメリットがあります!
「汁を捨てるのはもったいない…」と思える理由をチェックしてみましょう。
DHA・EPAを効率よく摂取できる
DHA・EPAは青魚に豊富に含まれる良質な脂質(オメガ3脂肪酸) で、健康維持に役立つことで知られています。
特にDHAやEPAは水に溶けやすい性質を持つため、加熱処理の過程で鯖の身から汁へ流れ出します。
大手食品メーカーのマルハニチロの調査によると、鯖缶のDHA・EPAの約1~2割が汁に溶け込んでいるとのこと。
つまり、汁を活用すれば、DHA・EPAをより効率的に摂取できるのです!
ビタミンB群やミネラルも含まれる
鯖缶の汁には、エネルギー代謝を助けるビタミンB群や、カルシウム・マグネシウムなどのミネラルも含まれています。
ビタミンB群には以下のような働きがあります。
- ビタミンB2(脂質の代謝をサポート)
- ビタミンB6(たんぱく質の代謝を助ける)
- ナイアシン(B3)(皮膚や粘膜の健康維持に役立つ)
また、カルシウムやマグネシウムは骨を強くするために重要なミネラルです。
牛乳や乳製品が苦手な方でも、鯖缶の汁を活用すれば手軽にミネラルを補うことができます。
料理に使うと旨味アップ!
「そのまま飲むのはちょっと苦手…」という方でも、料理に加えれば栄養を無駄なく摂取できます。
特におすすめの活用法は以下の3つ。
- 味噌汁やスープに加える → コクが増して美味しくなる!
- 炊き込みご飯の出汁に使う → 魚の旨味がしみ込んだご飯に!
- 煮物やパスタに加える → 旨味がアップして料理がワンランク上に!
「捨てるのはもったいない…」と感じたら、ぜひ料理に活用してみてください。
鯖缶の汁のデメリット・注意点
栄養豊富でメリットの多い鯖缶の汁ですが、いくつか気をつけるべきポイントもあります。
塩分が多い
鯖缶の汁には塩分が含まれているため、摂りすぎると塩分過多になってしまう可能性があります。
特に以下の方は、塩分の摂取量に注意が必要です。
塩分が気になる場合は、「減塩タイプの鯖缶」を選ぶのもおすすめです!
また、のちほど「塩分が気になる人のための対策」を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
そのままだと味が濃く、飲みにくい
鯖缶の汁は、鯖の旨味が凝縮されている反面、そのまま飲むと魚特有の風味が強い ため、飲みにくいと感じる方も多いです。
「ちょっとクセがある…」と感じたら、スープや味噌汁などに少しずつ加えてアレンジすると、美味しく取り入れやすくなりますよ。
どの鯖缶の汁が飲みやすい?種類別の特徴
「鯖缶の汁を飲みたいけど、どの種類が飲みやすいの?」と気になる方もいるのではないでしょうか?
鯖缶にはさまざまな種類があり、それぞれ味や塩分量、料理への活用しやすさが異なります。
そこで、鯖缶の種類ごとの特徴と、汁を飲む場合のおすすめ度をまとめました!
水煮缶
おすすめ度:★★★★★
- 塩と水だけのシンプルな味付け
- 汁にDHA・EPAが豊富に含まれている
- そのままでも料理に使いやすい
水煮缶は、最もシンプルな味付けの鯖缶 です。
塩と水のみで調理されているため、栄養が汁に溶け出しやすく、クセも少なめ。
「そのまま飲むなら水煮缶がベスト!」
また、味噌汁やスープ、炊き込みご飯など、どんな料理にも使いやすい のがメリットです。
味噌煮缶
おすすめ度:★★★☆☆
- 味噌のコクと甘みがある
- そのまま飲むには味が濃い
- 味噌汁や煮込み料理に活用しやすい
味噌煮缶は、味噌や砂糖で甘辛く味付けされた鯖缶 です。
そのため、汁に味噌の風味がしっかり溶け込んでおり、コクのある味わいが特徴。
ただし、そのまま飲むと塩分や甘みが強すぎる ため、飲みやすさはやや低め。
味噌汁や煮物の味付けに活用するのがおすすめ!
醤油煮・味付き缶
おすすめ度:★★☆☆☆
- 醤油や砂糖で味付けされている
- そのまま飲むには甘みが強い
- 煮物や炊き込みご飯向き
醤油煮や味付き缶は、醤油やみりん、砂糖でしっかり味付けされているため、甘みが強め。
そのまま飲むには少し味が濃すぎるため、汁を活用するなら炊き込みご飯や煮物に使うのがベスト!
結論:汁を飲むなら水煮缶、活用するなら他の鯖缶も!
- 汁をそのまま飲むなら → 水煮缶が一番おすすめ!
- 料理に活用するなら → 味噌煮缶や醤油煮缶もOK!
「鯖缶の汁を飲みたい」「料理に活用したい」という場合は、水煮缶を選べば間違いなし!
ただし、味噌煮缶や醤油煮缶の汁も、煮物や炊き込みご飯に活用すると美味しく楽しめますよ。
塩分が気になる人のための対策
鯖缶の汁にはDHA・EPAやビタミンB群が豊富に含まれていますが、一方で塩分も含まれているため、摂りすぎには注意が必要です。
特に、以下のような方は塩分の摂取量を意識すると良いでしょう。
- 高血圧が気になる方
- むくみやすい方
- 塩分制限をしている方
しかし、「栄養を無駄なく摂りたいけど、塩分が気になる…」という方も多いはず。
そこで、塩分を抑えながら鯖缶の汁を活用する方法 をご紹介します!
減塩タイプの鯖缶を選ぶ
最近では、塩分控えめの「減塩タイプ」の鯖缶 も販売されています。
通常の水煮缶よりも塩分が少なく、汁も活用しやすいのがメリット です。
「減塩」「塩分控えめ」と記載されたものを選ぶと、塩分を抑えつつ栄養を摂ることができます。
メーカーによって塩分量が異なるため、成分表示をチェックして選ぶのがポイントです。
「鯖缶の栄養を摂りたいけど、塩分が気になる…」という方には、まず減塩タイプの鯖缶を試してみるのがおすすめ!
鯖缶の汁を水で薄めて使う
そのまま飲むと塩分が濃いと感じる場合は、水で薄めると塩分を調整しやすくなります。
味噌汁やスープに加える場合は、だし汁やお湯で薄めると塩味が和らぎます。
炊き込みご飯に使う場合は、水を少し多めに入れて炊くことで、塩分を抑えることができます。
水で薄めるだけで塩分量を調整できるので、簡単に実践できる方法です。
カリウムを多く含む食材と一緒に摂る
カリウムには体内のナトリウム(塩分)を排出する働きがある ため、鯖缶の汁と一緒に摂ることで、塩分の影響を和らげることができます。
カリウムが豊富な食材は、ほうれん草、小松菜、キャベツなどの葉物野菜、バナナやアボカドなどのフルーツ、じゃがいも、さつまいも、わかめや昆布などの海藻類があります。
たとえば、「鯖缶の汁+野菜たっぷりの味噌汁」や「鯖缶の汁+わかめスープ」 のように組み合わせると、塩分の摂りすぎを防ぎながら栄養をしっかり摂ることができます!
汁の量を調整しながら使う
「鯖缶の汁は栄養豊富だけど、全部使うのは塩分が気になる…」という場合は、料理に少しずつ加えるのもおすすめです。
最初からすべての汁を使うのではなく、味を見ながら少しずつ加えると、塩分の摂取量をコントロールしやすくなります。
また、汁を活用する際は、味噌や醤油などの調味料を控えめにする と、全体の塩分量を抑えることができます。
続いて、「鯖缶の汁の活用法!おすすめの使い方3選」 をご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
鯖缶の汁の活用法!おすすめの使い方3選
鯖缶の汁はそのまま飲むだけでなく、料理に活用すると旨味がアップし、栄養も無駄なく摂取できます。
ここでは、手軽にできて美味しく仕上がるおすすめの使い方3つ をご紹介します!
味噌汁やスープに加える
鯖缶の汁は、魚の旨味が凝縮されているため、味噌汁やスープの出汁として活用すると美味しく仕上がります。
味噌汁に加える場合
いつもの味噌汁に鯖缶の汁を大さじ1~2杯加えるだけで、コクと旨味がアップします。
特に、豆腐やわかめ、ネギなどの具材と相性抜群です。
スープに加える場合
コンソメスープやトマトスープに鯖缶の汁を加えると、魚の風味がほんのりプラスされて深みのある味わいに。
塩分が気になる場合は、スープの味付けを少し控えめにするとバランスが取れます。
炊き込みご飯の出汁に使う
鯖缶の汁は、炊き込みご飯の出汁として使うと、ご飯にしっかりと魚の旨味が染み込みます。
作り方の基本
- お米2合を洗い、通常の水加減より大さじ2杯分の水を減らす。
- 鯖缶の汁を大さじ2杯加え、通常どおり炊飯する。
- 仕上げに鯖の身をほぐして混ぜれば、栄養満点の炊き込みご飯の完成。
しょうがやごまを加えると風味がアップし、より美味しく仕上がります。
煮物やパスタの隠し味に
鯖缶の汁は、煮物やパスタに少量加えると、魚の旨味がプラスされて深い味わいに。
煮物に加える場合
肉じゃがや大根の煮物に、鯖缶の汁を大さじ1杯ほど加えると、和風の旨味が引き立ちます。
醤油やみりんと相性が良いため、煮込み料理に使うのもおすすめです。
パスタに加える場合
オイル系のパスタ(ペペロンチーノや和風パスタ)に鯖缶の汁を小さじ1~2杯加えるとコクが増します。
にんにくやオリーブオイルとの相性も良く、風味豊かな一品に仕上がります。
鯖缶の汁をそのまま飲むのが苦手な方でも、料理に加えることで美味しく活用できます。
ぜひ試してみてくださいね。
結論:鯖缶の汁は活用すればメリットたくさん!
鯖缶の汁にはDHA・EPAやビタミンB群などの栄養が豊富に含まれています。
ただし、塩分が多いため、そのまま飲むよりも料理に活用するのがベストです。
- 味噌汁やスープに加える と、旨味が増して美味しく仕上がる
- 炊き込みご飯の出汁にする と、ご飯に風味が染み込み栄養満点
- パスタや煮物にちょい足し すると、コクが深まりワンランク上の味わいに
こうすれば、栄養も旨味も無駄なく摂取できます!
鯖缶を食べるときは、ぜひ汁まで賢く活用してみてくださいね。
そして、鯖缶の身をお弁当に活用したいときは、「匂い対策」も大切です!
「お弁当に鯖缶を入れたいけど、汁はどうする?」
「鯖缶をお弁当に入れると、匂いが気になりそう…」
そんなお悩みを解決するために、匂いを抑えるコツや、美味しく食べるアレンジ法 をまとめました!
鯖缶をお弁当に入れる際の注意点を知りたい方は、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください。