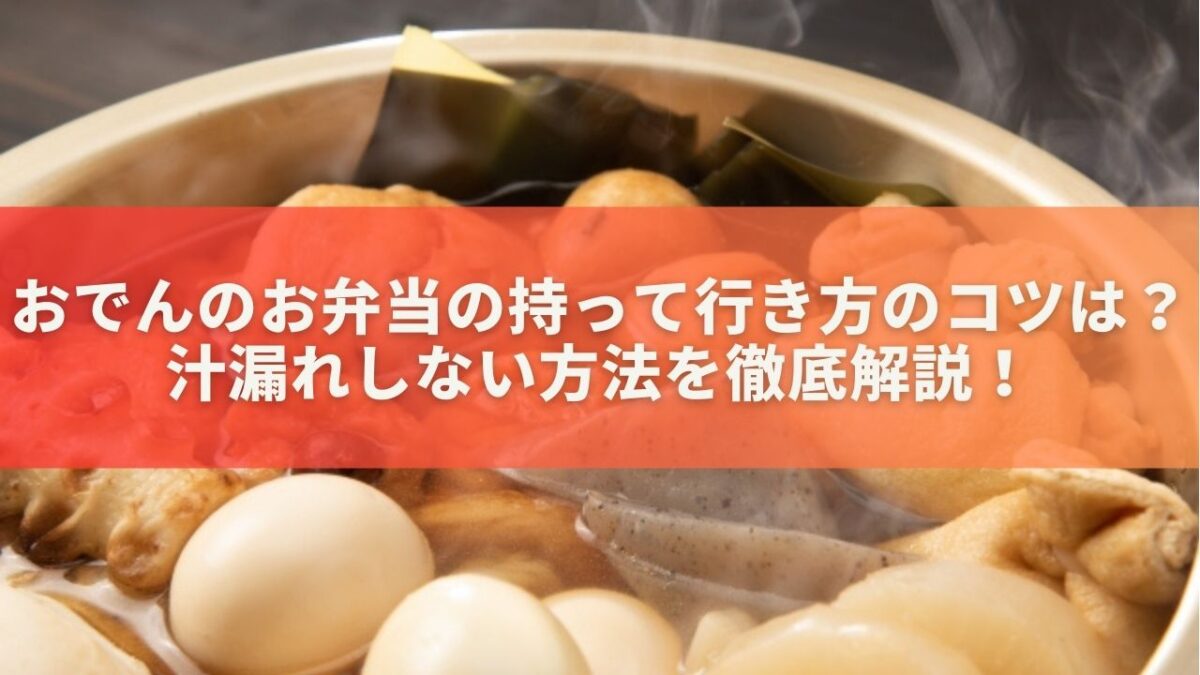夕食の残りのおでんをお弁当で持って行きたいとき、理想的な方法があればどれほど便利でしょうか。
しかし、「汁が漏れたらどうしよう」と不安になる方も多いのでは?
どんなに水分を取り除いても、時には汁がこぼれてしまうことがあります。
また、汁をしっかり持っていきたい方も多いはずです。
この記事では、汁漏れを防ぐための具体的なテクニックや、おすすめの便利グッズを徹底的に解説します。
おでんを美味しく持って行くためのコツを学べば、どこでも手軽におでんランチが楽しめますよ♪
おでんのお弁当の持って行き方のコツは?
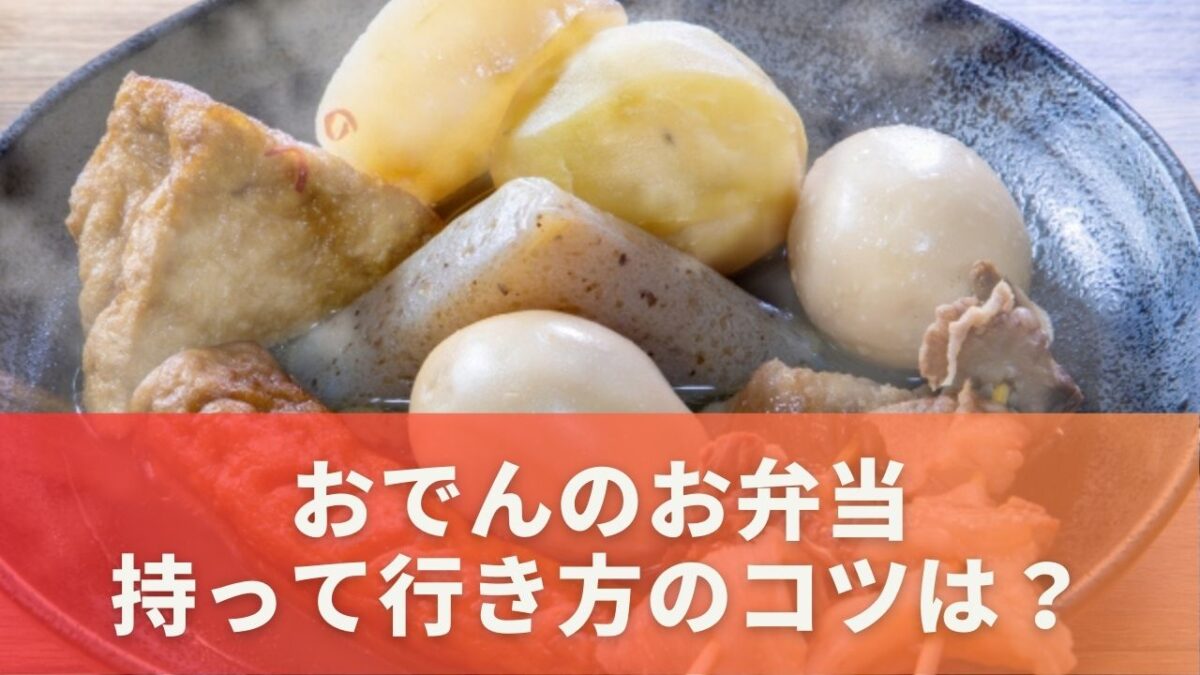
おでんをお弁当に詰める際には、汁漏れを防ぐためのいくつかの工夫があります。
まず、汁を吸収できるカップや、吸水性の高い食材を底に敷くと効果的です。
また、密閉できる弁当箱を選ぶことで、汁が漏れるリスクを大幅に減少させることができます。
ナフキンやバッグが汁で濡れてしまうのを防ぐためにも、こうした対策は重要です。
おでんの詰め方には、汁なし・汁ありといったさまざまなスタイルが存在しますが、それぞれに特有のコツがあります。
これから、その方法や役立つアイテムについて詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
汁なしでおでんを詰める方法
汁を含まない状態でおでんをお弁当に詰める際には、以下の2つの効果的な方法があります。
吸水性カップを利用する
通常のお弁当カップよりも優れた機能を持つ吸水性のカップを使うと、汁漏れを防げます。
このカップは、液体や油をしっかりと吸収するため、練り物の油分も取り込んでくれます。
さらに、前日の夜にバットや皿にキッチンペーパーを敷き、その上に具材を置いて冷蔵庫で一晩水切りを行うと、より一層汁漏れのリスクを減らすことができます。
鰹節を敷く
お弁当カップに鰹節を敷いた後、その上におでんの具を乗せることで、汁漏れを防ぐことが可能です。
鰹節は食べられるので安心です。
この方法も、同様に前日の夜に具材を水切りしてから詰めると効果的です。
この技は他の汁気の多いおかずにも応用できるので、ぜひ試してみてください!
汁ごと入れる際のベストな方法
汁を含めておでんを詰める場合、以下の方法が効果的です。
漏れない容器の選択がポイントですよ。
ロック機能付きタッパーを活用する
漏れ防止に優れたロック機能付きタッパーを選びましょう。
特に「オクソー」というブランドは、機能性とデザイン性に優れた製品が揃っています。
私自身もいくつか持っており、普通のタッパーよりもおしゃれにおでんを楽しむことができます。
さらに、電子レンジにも対応しているため、温め直しも簡単です。
スープジャーを使う
スープジャーは基本的に漏れにくく、保温機能が付いているため、手軽に温かいおでんを持ち運べます。
使用する際は、まず熱湯でジャーを温め、その後、鍋でしっかり加熱したおでんを汁ごと入れると、温かさをキープできますよ。
このジャーはおでんだけでなく、野菜スープやシチューにも活用できるため、非常に便利です。
おでんの汁漏れを防ぐための確実な方法

おでんの汁が弁当箱から漏れないようにするためには、以下の2つのポイントを意識しましょう。
- 汁気を抑える工夫をする
まずは、具材の水分をしっかり取り除く工夫を試みてください。たとえば、前日に具材をキッチンペーパーで包み、水切りをすることで、余分な汁を減らすことができます。 - 密閉性の高い容器を選ぶ
次に、ゴムパッキン付きの密閉性のある弁当箱を使用することが重要です。密閉性のない容器では汁が漏れてしまう可能性が高いため、特に曲げわっぱのようなものは避けるべきです。選ぶ際は、漏れにくい設計の弁当箱を確認しておくと良いでしょう。
これらの対策を講じれば、安心しておでんをお弁当に詰められます。
まとめ
おでんはお弁当に入れることができます♪
「漏れないかな」と不安な方も安心してください。
しっかりとした汁漏れ対策を講じれば、問題なく詰められます。
私が実践している方法は、まずバットや皿にキッチンペーパーを敷き、その上におでんの具材を置き、ラップをして冷蔵庫で保存します。
これを前夜に行うと、余分な汁がしっかり取れるので、朝は簡単に詰めるだけで済みます。
もし汁なしでおでんを持ち運びたい場合、この方法を参考にしてみてくださいね。
また、汁ごと入れたいときは、漏れない容器を使うことで安心して持ち運ぶことができます。
これで、おでんのお弁当も安心して楽しめますね!
また、前日に準備する場合や、余ったおでんを活用したいときは、保存方法にも気をつけましょう。
「前日に作っておいたおでん、翌日まで大丈夫かな?」
「余ったおでんはどう保存すればいい?」
そんな疑問を感じたら、こちらの記事をチェック!
➡ おでんの日持ちはどれくらい?常温・冷蔵・冷凍の保存期間と正しい保存方法を解説
作り置きしておでんを活用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。