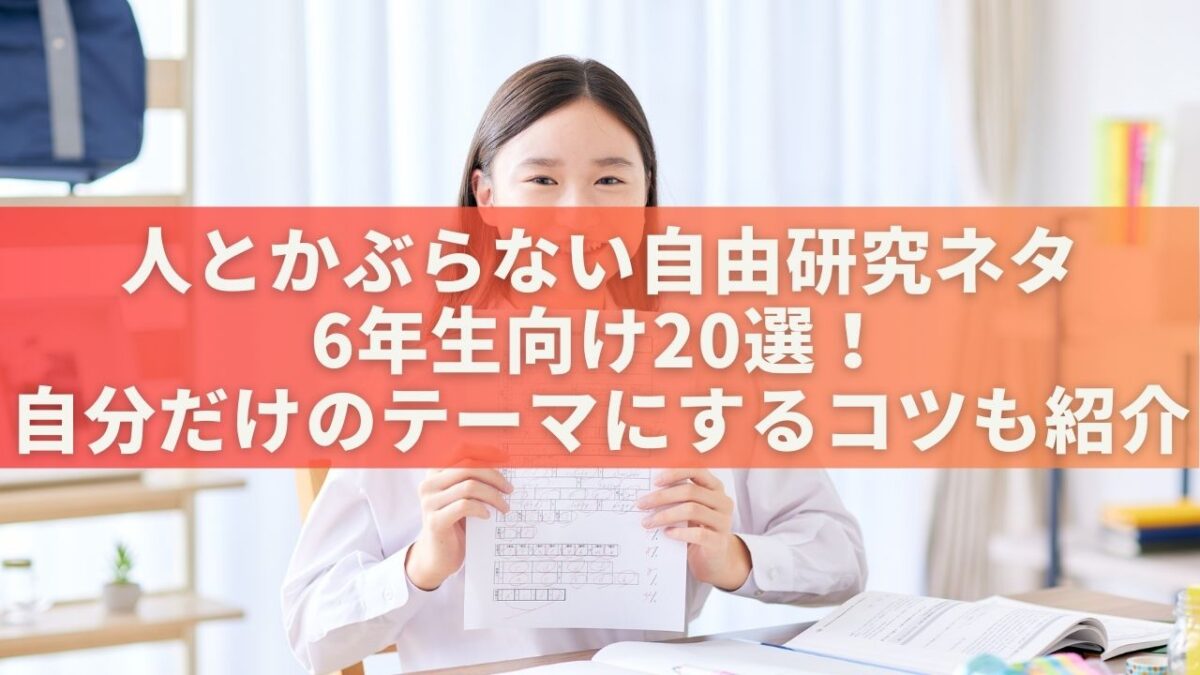「自由研究、今年はどうしよう…」
「また同じようなネタになりそう…」
そんなふうに悩んでいる6年生や保護者の方に向けて、“人とかぶらない自由研究”のアイデアをたっぷり20個ご紹介します!
実験・工作・面白いテーマから、短時間でできるものまで、6年生の興味にぴったりな内容を集めました。
さらに、自分だけのオリジナルな研究に仕上げるコツもセットで解説。
見せ方やまとめ方をちょっと工夫するだけで、自由研究がグッと楽しく、自信の持てるものになりますよ。
「これならできそう!」「ちょっとおもしろそう!」と感じるテーマがきっと見つかるはず。
今年の自由研究、ちょっと特別にしてみましょう!
人とかぶらない自由研究ネタ【6年生向け20選】
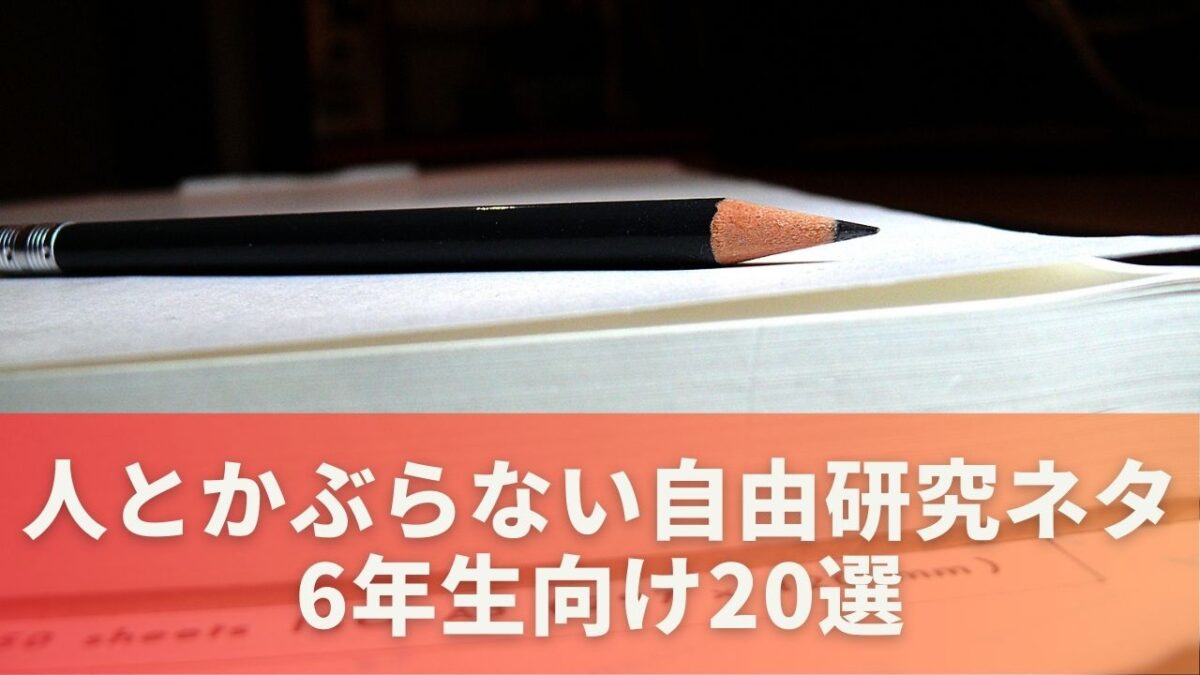
6年生の自由研究、どうせなら“人とかぶらない”ものにしたいですよね。
ここでは、実験・工作・おもしろテーマなど、オリジナリティたっぷりのアイデアを20個集めました!
気になるテーマを見つけて、自分だけの自由研究にチャレンジしてみてください。
みんなが「やってみたい!」と思える面白テーマ【5選】
ちょっと笑える、見た目も楽しい、友達に見せたくなるような“エンタメ系”の研究はこちら。
1. 世界一まずいジュースをつくってみた
● 準備するもの
いろんな食材(調味料・飲み物・フルーツなど)、コップ、記録ノート
● やり方
- 家にある材料を組み合わせて「ジュース風ドリンク」を何種類か作る
- 飲めるけど変な味を目指す!(辛すぎ・甘すぎはNG)
- 家族で試飲して、感想をメモに取る
- 見た目・におい・味・インパクトなどで評価してランキングに
● まとめ方のコツ
- 味の感想をグラフや表でまとめると面白い
- 「飲んだ瞬間の表情写真」などを入れると盛り上がる
- 衛生管理と安全性には注意することも書いておこう
2. 方言しりとり選手権!
● 準備するもの
方言を知っている人(家族・祖父母など)、メモ帳、方言辞典(ネットでもOK)
● やり方
- 家族や親戚に聞いて方言を集める
- しりとり形式で使えるかどうかをチェック
- どこの地域で使われているか、意味を調べてまとめる
- 方言だけでしりとり大会を実施!
● まとめ方のコツ
- 方言の読み・意味・使い方を表にするとわかりやすい
- 実際の会話での使用例を入れるとリアリティが出る
- 「しりとりに使えなかった珍しい方言」も番外編で紹介してみよう
3. 10円玉で作る鏡アート
● 準備するもの
古い10円玉、酢、塩、綿棒、割りばし、新聞紙、手袋
● やり方
- 酢と塩を混ぜて「磨き液」を作る
- 綿棒で10円玉をこすって、ピカピカにする
- 鏡のように光る面に、模様や文字をつけていく
- 変化をビフォー・アフターで記録
● まとめ方のコツ
- 酸化・還元の仕組みを簡単に解説すると理科的に◎
- ピカピカになった10円玉の写真を並べて作品集風に
- どれくらい磨いたらどのくらい光るか?比較してみても良い
4. 光のマジック文字実験
● 準備するもの
黒い紙、水、筆、ペン、懐中電灯、白い壁
● やり方
- 水で薄く文字を書く(乾くと見えなくなる)
- 光を当てる角度を変えて、文字が浮かび上がる様子を観察
- 他の液体(ジュース・牛乳など)でも試してみる
- 一番きれいに浮かび上がる条件を探す
● まとめ方のコツ
- 写真を使って「見えない → 見える」の変化を見せると説得力あり
- どの素材でうまくいったかを表にまとめよう
- 目の錯覚や光の反射について簡単な説明を加えると深みが出る
5. スライムで指紋調査!
● 準備するもの
スライム(自作でもOK)、紙、油性ペン、ルーペまたはスマホカメラ
● やり方
- 家族の指をスライムに押し当てて指紋を型取り
- スライムにできた溝を観察・記録
- 名前を伏せて「この指紋は誰?」クイズにしてみる
- 指紋のパターン(渦巻き・弓形など)を分類
● まとめ方のコツ
- それぞれの指紋の特徴を図やスケッチでまとめよう
- 指紋の種類や働きを調べて「豆知識」として紹介
- 実験だけでなく「誰の指かわかったかどうか」も記録に入れると面白い
理科が好きな人におすすめ!ワクワク実験テーマ【6選】
科学のしくみや自然の不思議を、自分の手で確かめてみよう!
6. 電気が通る?通らない?身近な素材しらべ
● 準備するもの
乾電池、豆電球、導線、クリップ、アルミホイル、えんぴつ、プラスチック、紙など
● やり方
- 電池・豆電球・導線をつないで「通電チェック装置」を作る
- 素材ごとに間に挟んで、電球がつくかどうかを確認
- いろんなもの(木、金属、布など)で試して記録
● まとめ方のコツ
- 表に「素材名・通ったか・光の強さ」などを整理すると見やすい
- 結果から「電気を通す共通点」を考察できると◎
- 絵や写真を使って回路図を入れると理科っぽさが出る
7. 氷はどう浮かぶ?条件別にチェック!
● 準備するもの
水、砂、塩、色水、製氷皿、透明なコップ、スプーン、記録ノート
● やり方
- 普通の氷、砂入り氷、塩水で作った氷、色付き氷をそれぞれ作る
- 同じサイズのコップに水を入れて、1つずつ浮かべる
- 浮き方や沈み方を観察し、時間とともに変化を記録
● まとめ方のコツ
- 氷の状態と浮き方の関係を写真で見せると分かりやすい
- 「なぜ沈んだのか?」に着目して、密度や比重の説明を入れるとGOOD
- ビフォー・アフター形式の写真で比較してみよう
8. 植物に音楽を聴かせて育ててみた
クラシック/ロック/無音で植物を育てて、どんな違いが出るか観察してみよう!
音の影響で成長に差が出るのか?意外な結果が出るかも?
● 準備するもの
- 同じ種類の植物(例:豆苗、ホウセンカなど)を3つ
- 音楽を流すためのスマホやスピーカー
- メジャーまたは定規、ノート、写真を撮るためのスマホ
- 植木鉢または容器、土(同じ条件にする)
● やり方
- 植物を3つ用意し、それぞれ同じ環境(日当たり・水やり)で育てる
- 1つ目にはクラシック音楽、2つ目にはロック、3つ目は無音の状態にする
- 毎日決まった時間に音楽を15〜30分流す
- 毎日、植物の高さや葉の数を記録していく
- 1〜2週間後に成長の違いを比べて、写真やグラフでまとめる
● まとめ方のコツ
- 成長の変化を折れ線グラフや写真の並べ方で見せるとわかりやすい
- 「どの音楽でよく育った?なぜそう思う?」など自分の考察をしっかり書く
- 「もっと実験期間を延ばしたらどうなるか?」など次への発展も書けると◎
9. ろ過装置を作って水をきれいにしよう
● 準備するもの
空のペットボトル、ガーゼ、砂、炭(活性炭)、綿、カップ、泥水(水+土)
● やり方
- ペットボトルを逆さにして、底を切り取り「ろ過装置」にする
- 下から綿→炭→砂→ガーゼの順で入れる(層にして)
- 上から泥水を注ぎ、出てくる水の透明度を観察
- ろ材の順番を変えた場合も比較すると面白い
● まとめ方のコツ
- 使用した材料と水の変化を図にして比較するとわかりやすい
- 「なぜ炭が効果的?」などのしくみを調べて説明すると深みが出る
- 実験結果と「環境への応用例」を組み合わせても◎
10. 洗剤の泡くらべ実験
● 準備するもの
数種類の洗剤(食器用、ボディソープなど)、水、計量カップ、ストロー、タイマー、コップ
● やり方
- 各洗剤を同じ量で水に薄めて用意
- ストローで30秒ずつ泡立てて、泡の高さ・もち時間を計測
- 同じ条件で繰り返し、平均を取る
● まとめ方のコツ
- グラフにして「泡の高さ・もち・におい」などの比較を見せる
- 「なぜこの洗剤が泡立ちやすいのか?」の理由を考える
- 実験の工夫(時間・量を揃えること)も研究に含めよう
11. サイコロ100回!出目は本当に平等?
● 準備するもの
サイコロ(1つ)、ノート、記録用紙、定規、色ペン、集計表
● やり方
- サイコロを100回振って、出た目を1回ずつ記録
- 目ごとの回数を集計して、出やすい数字がないかチェック
- 結果を円グラフ・棒グラフでまとめる
● まとめ方のコツ
- 表やグラフにすると統計っぽくなってレベルアップ!
- 本当に平等になったかを考察しよう(振るクセの影響もあるかも?)
- 回数を200回に増やすとさらに信頼性アップ!
作って楽しい!見せてびっくりの工作テーマ【5選】
作って楽しい・飾ってうれしい・動かしてびっくりの工作ネタはこちら!
12. 手作り風力発電おもちゃ
● 準備するもの
小型モーター、LEDライト、羽根(紙 or プラスチック)、ストロー、電線、紙コップなど
● やり方
- モーターとLEDをつないで配線を確認
- 羽根をストローや割りばしで固定して、風で回るようにセット
- 扇風機や口で風をあてて、LEDが光るか確認
- 羽根の形や角度を変えて効果を比べる
● まとめ方のコツ
- 光るまでの条件(風の強さ・羽根の形)を表や写真でまとめよう
- うまくいかない時の原因と改善点も記録すると◎
- 発電のしくみも簡単に解説できると理科的に深まる
13. 紙ストローで“強い橋”を作ろう
● 準備するもの
紙ストロー(20〜30本)、のり or グルーガン、紙、重り(消しゴムや本など)
● やり方
- 橋の形(アーチ・三角・平行など)を決めて設計図を描く
- ストローを切って土台・柱・斜め補強を作る
- 重さに耐えられるかテストして、結果を記録
- 他の形と比較実験してもOK!
● まとめ方のコツ
- 図や設計図と、完成写真をセットで紹介
- どんな形が一番強かったか?なぜか?を考察する
- 「もし本物の橋だったら?」と社会や現実とつなげても◎
14. 紙コップスピーカーをつくって音を聞く
● 準備するもの
紙コップ2個、磁石、銅線、スマホ or 音楽プレーヤー、カッター、セロハンテープ
● やり方
- 紙コップの底に磁石を貼り、周囲に銅線をぐるぐる巻いて固定
- スマホのイヤホンジャック(または変換ケーブル)に導線をつなぐ
- 音を流すと、スピーカーが小さく振動し、音が聞こえるか試す
- コップのサイズ・巻き方で音の大きさを変えてみる
● まとめ方のコツ
- 音が出るしくみ(電気→磁力→振動)を図で説明すると◎
- 銅線の巻き数と音量の関係を比較してグラフにすると説得力UP
- 写真を交えて、作り方の手順も載せると読者にも親切!
15. 太陽で走るミニカーに挑戦
● 準備するもの
ソーラーパネル付きミニカーキット(100均や通販で購入可)、ドライバー、太陽光 or 懐中電灯
● やり方
- 説明書に従ってミニカーを組み立てる
- 太陽の下に出して走らせ、動き方を観察
- 室内(懐中電灯)でも動くか?比較して記録
- ソーラーパネルの角度を変えて反応を見る
● まとめ方のコツ
- 実験結果を「光の強さとスピードの関係」で表にすると理科的!
- 太陽以外の光源との違いにも触れてみよう
- 「再生エネルギー」やSDGsのテーマにもつなげられる
16. 百人一首をマンガにしてみた!
● 準備するもの
百人一首の本または一覧、ノート or マンガ用紙、ペン、色えんぴつ
● やり方
- 好きな百人一首を数首選ぶ
- 現代語訳と、情景・感情を自分なりに解釈する
- それを4コマ or 1ページマンガにして表現
- 一首ごとに簡単な解説コメントを入れる
● まとめ方のコツ
- 和歌の意味とマンガの内容がつながっているかがポイント
- 自分なりの解釈や「こんな風に想像した!」という工夫が評価される
- 作品集風にして提出すると、読みやすくて印象も良い
時間がない人でも大丈夫!10分でできる自由研究【4選】
「時間がない…でも何かやりたい!」そんな人向けに、すぐできて楽しいテーマを。
17. 牛乳アート実験
● 準備するもの
牛乳、食紅または水性インク、台所用洗剤、皿、綿棒
● やり方
- 皿に牛乳を少し注ぐ
- 食紅を1〜2滴たらす(数色あるときれい)
- 綿棒に洗剤をつけて、牛乳にそっと入れる
- 色がパッと広がる様子を観察する
● まとめ方のコツ
- 色の広がりを動画や連続写真で記録
- 「なぜ色が動くのか?」表面張力の説明を簡単に加えると◎
- 色の組み合わせでアート作品としても楽しい
18. 火山のミニ噴火!
● 準備するもの
重曹、酢、食紅、粘土 or 紙粘土(火山の形を作る用)、カップ、スプーン
● やり方
- 粘土で小さな火山の模型を作る(真ん中にくぼみをつくる)
- 中に重曹+食紅を入れる
- 上から酢を注ぐと…ブクブクと「噴火」!
- 材料の量を変えて、噴火の勢いを比べても楽しい
● まとめ方のコツ
- 火山の形や色で“自分だけの火山”を作ると個性が出せる
- 噴火のしくみ(化学反応)について簡単に触れると◎
- ビフォー・噴火中・噴火後を写真でまとめると迫力あり
19. 鏡で“世界を逆さま”にしてみた
● 準備するもの
鏡(手鏡または大きめの鏡2枚)、紙、ペン、定規
● やり方
- 鏡を斜めに合わせて「鏡のトンネル」を作る
- 物を映して、左右反転・上下反転を観察
- 同じ文字を写してみて、どこが反対になるかを記録
- 映る角度や向きを変えて変化をチェック
● まとめ方のコツ
- 図解で「どう見えるか」を説明すると分かりやすい
- 鏡文字・左右反転のしくみを調べて書いても◎
- “鏡を使ったアート作品”風にしても楽しい!
20. 地元の駅名・町名の由来調べ
● 準備するもの
地図、図書館の郷土資料 or インターネット、ノート、色ペン
● やり方
- 自分が住んでいる町や近くの駅の名前の由来を調べる
- 地図に印をつけて、意味・歴史をメモ
- 写真を撮ったり、現地に行けるなら散歩しながら取材してみる
- いくつかの地名を比べて傾向を探す
● まとめ方のコツ
- 地図と写真を組み合わせてビジュアル的にまとめよう
- 「昔の人はなぜこの名前をつけたのか?」を考察すると◎
- 周辺の学校・川・山なども一緒に調べてみると広がる!
以上、6年生にぴったりな「人とかぶらない自由研究ネタ」を20個ご紹介しました。
自分の興味や得意なことに合わせて、楽しく取り組んでみてくださいね。
なお、毎日の学習や宿題にも使える「10分でできる自学」ネタを知りたい方は、こちらの記事も参考にどうぞ!
自分だけの自由研究にするための3つのコツ
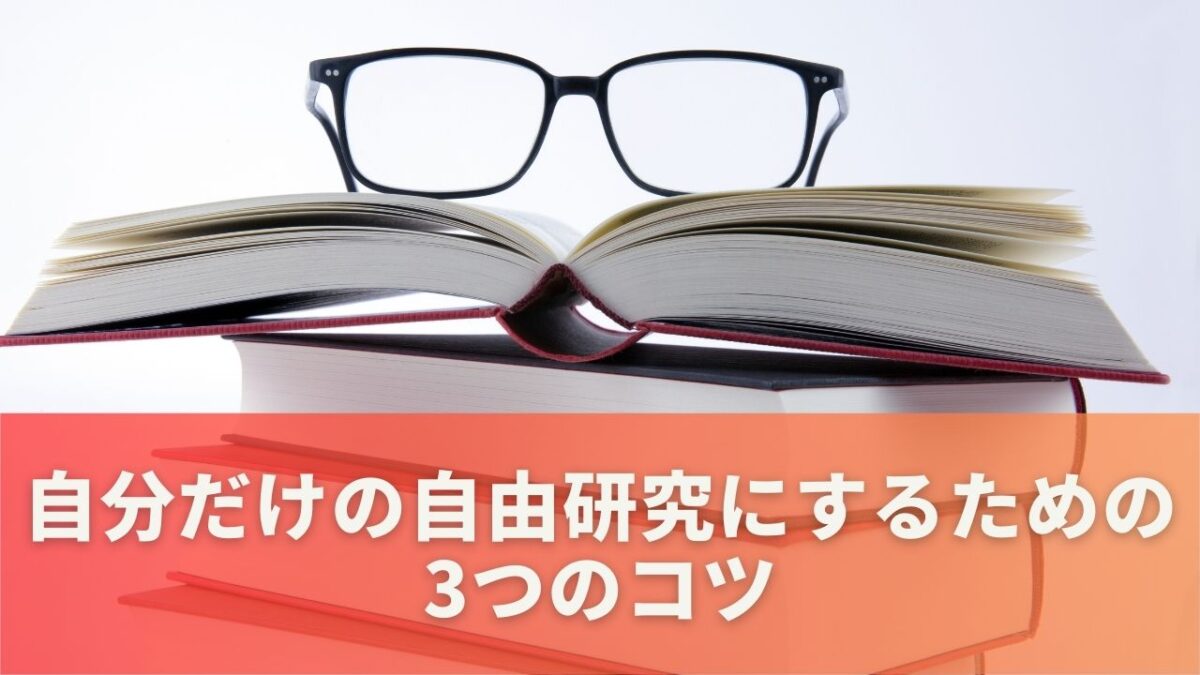
自由研究で「人とかぶらない」ものにしたいなら、テーマ選びも大切ですが、まとめ方や見せ方にも工夫してみましょう。
同じテーマでも、「まとめ方」がちょっとちがうだけで、まったく違う研究に見えることもあるんです!
ここでは、自分だけの研究にするための3つのコツを紹介します。
コツ①:見せ方を工夫すると、研究がもっと伝わる!
どんなにすごい研究でも、見せ方がごちゃごちゃだと、よく伝わりません。
逆に、見せ方をちょっと変えるだけで「すごい!」って思ってもらえることもあります!
おすすめのまとめ方:
- 新聞みたいに、見出し・写真・コラムを使ってまとめる
- スライド(発表用の資料)みたいに順番に見せていく
- 研究ノートみたいに、手書きでしっかりまとめる
- オリジナルキャラやイラストで、楽しく説明する
こんな工夫もおすすめ:
- 実験の様子を写真に撮って貼る
- 結果をグラフや表でわかりやすく見せる
- 「わかったこと」「びっくりしたこと」を自分の言葉で書く
コツ②:くらべてみると、結果がぐっとおもしろくなる!
ひとつだけやるよりも、いくつかの条件を比べてみると、もっとおもしろくなります。
たとえば:
- 洗剤の泡をくらべて、どれが一番長持ちするか調べる
- 火山の実験で、酢の量を変えて「どれがいちばんふん火するか」調べる
- 音楽と植物の実験で、「どんな音楽だとよく育つか」くらべてみる
ポイント:
- 3つくらいのパターンをくらべるのがちょうどいいよ
- グラフや表を使って見せると、先生にも伝わりやすい
- 結果を見て、「なんでこうなったのかな?」と考えてみよう
コツ③:自分の気づきや思ったことも忘れずに!
自由研究は「やっておわり」じゃもったいない!
やってみてどうだった?なにを感じた?をしっかり書くと、あなたらしい研究になります。
こんなふうに書いてみよう:
- 実験してみたら、意外な結果になっておどろいた
- 今度は別の材料でも試してみたいと思った
- この研究を通して、○○がもっと好きになった!
おすすめの流れ:
- なんでこの研究をやろうと思ったのか?
- どんなふうにやったのか?(実験・調べたこと)
- わかったこと・気づいたこと・びっくりしたこと
- もっとやってみたいこと、工夫したいこと
この流れでまとめれば、「人とかぶらない自由研究」が完成します!
まとめ|かぶらない自由研究は「じぶんらしさ」でできる!
自由研究って、「どんなテーマにしよう?」「他の子とかぶらないかな?」と悩むことも多いですよね。
でも、テーマ選びだけじゃなく、やり方やまとめ方をちょっと工夫するだけで、自分らしい研究にすることができます。
この記事では、6年生にぴったりな人とかぶらない自由研究ネタを20個紹介しました。
面白いもの、実験、工作、そして10分でできるものまで、いろんなアイデアがありましたね。
さらに、自分だけの研究にするためのコツとして
- まとめ方のアイデア
- 比べる工夫
- 気づきや感想の書き方
なども紹介しました。
大切なのは、「やってみたい!」と思えるテーマを選んで、じぶんの工夫や考えをしっかり入れること。
そうすれば、どんなテーマでも、世界にひとつだけの自由研究になりますよ。
ぜひこの記事をヒントに、楽しくて、自分らしい自由研究にチャレンジしてみてください!
6年生におすすめの関連記事
➡ 他の学年の自由研究ネタも見てみたい方へ
【小学生向け】人とかぶらない自由研究 1年生〜6年生まで学年別アイデア80選
➡ 自主学習のネタが切れたときはこちら
【小6生必見!自学のネタが切れたときの学習テーマ20選と効果的な7つの対処法】
➡ 短時間でできる学習アイデアもチェック!
【小学6年生向け10分でできる自学24選とポイント!驚くほど簡単!】
➡ 学年別の自主学習ネタを探したい方はこちら
【小学生の自主学習ネタ192選!学年別にすぐ使えるアイデアとコツを紹介】