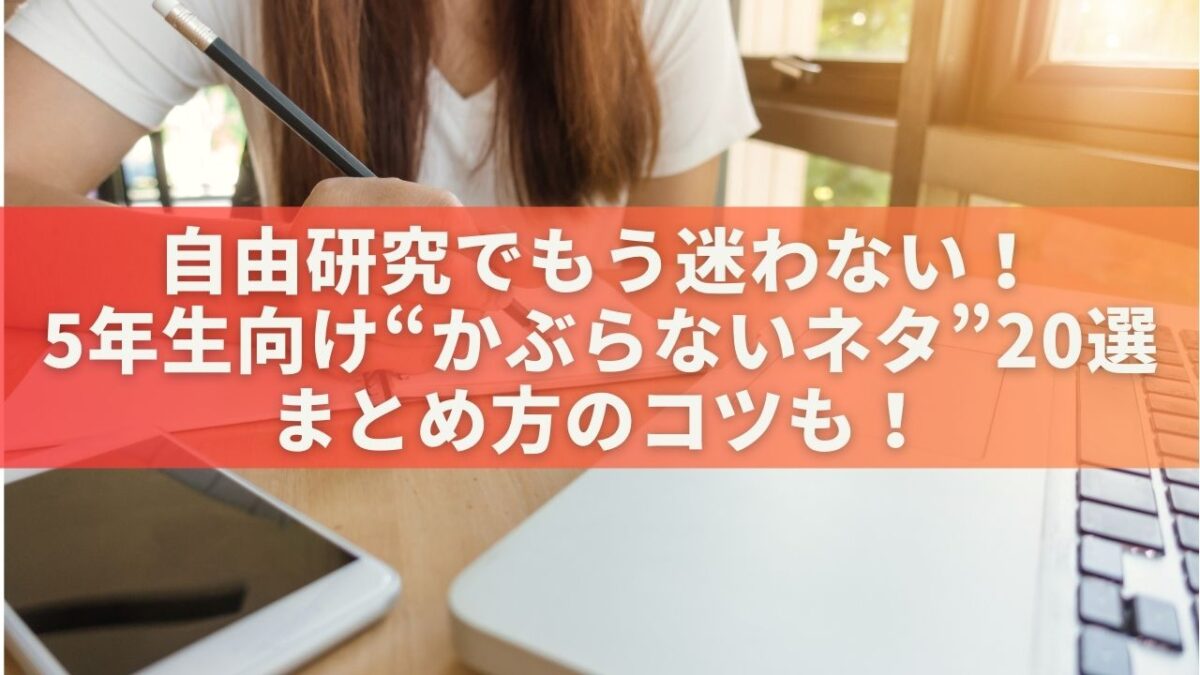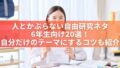「えっ、それ自由研究でやったの?すごい!」
そんなふうに友だちに言われたくないですか?
自由研究って、テーマ選びがいちばんむずかしい…。
でも、ちょっとユニークなアイデアや、ちょっとした工夫で、だれにもマネできない“自分だけの自由研究”が作れちゃいます!
この記事では、5年生にぴったりな「人とかぶらない自由研究ネタ」を20個まとめてご紹介。
さらに、まとめ方や工夫のコツもバッチリ紹介するので、自由研究でもう迷わない!
楽しく取り組めるテーマが、ここにそろっています。
もう迷わない!5年生向け“かぶらない自由研究ネタ”20選
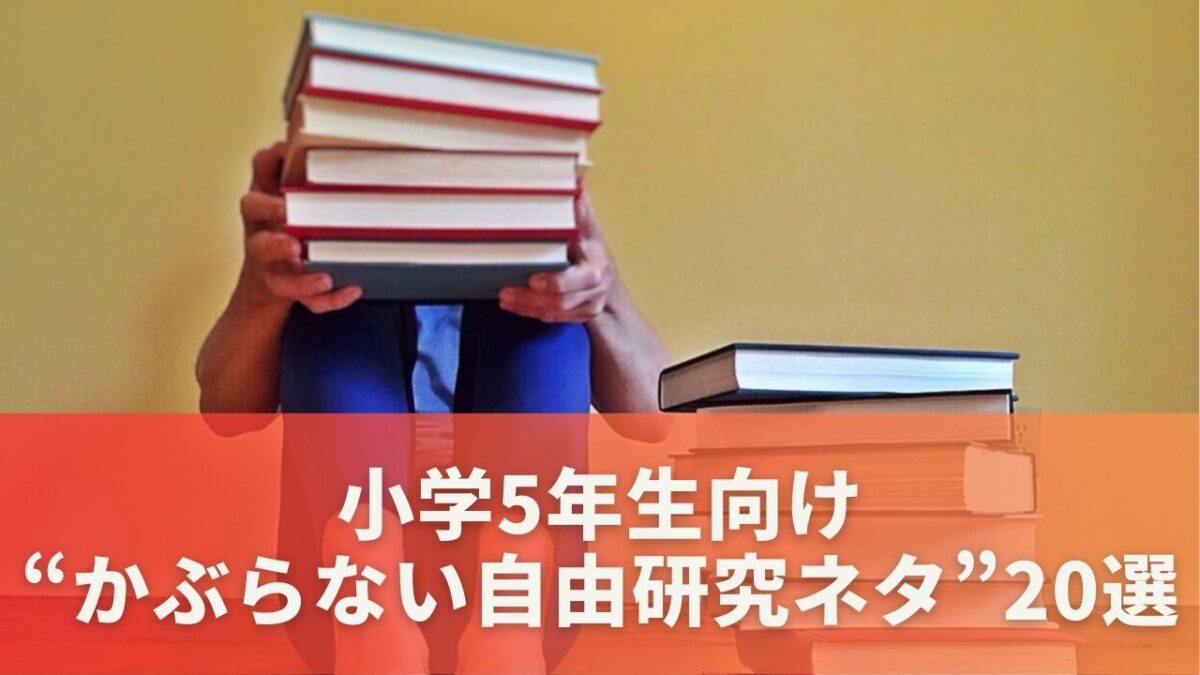
毎年の自由研究、「テーマが思いつかない」「同じようなネタばかりで困る…」と感じていませんか?
ここでは、5年生にぴったりで“人とかぶらない”ユニークな自由研究のアイデアを20個ご紹介します!
楽しくて、やってみたくなるものばかり。
友だちとちょっと差がつく自由研究、きっと見つかりますよ!
えっ、それやったの⁉ 思わず試したくなるユニークテーマ【5選】
1. ジュースは何色まで作れる?自作カラードリンク実験
● 準備するもの
食紅、果汁、コップ、ストロー、水、スプーン、記録ノート
● やり方
- いろんな色を混ぜて自分だけのカラージュースを作ってみる
- 味や香りは関係なく、見た目をとにかく面白く!
- できた色を記録して、名前をつけても楽しい
● まとめ方のコツ
- 色ごとのレシピ(混ぜた分量)を表にすると◎
- 作ったジュースを写真にとって一覧にすると見ごたえあり
- 「一番気に入った色」「もっとこうしたい」を感想に!
2. 身の回りの“へんてこ単位”を調べてみた!
● 準備するもの
定規、はかり、メジャー、ノート、家にあるいろんな道具や食べ物
● やり方
- 「1たいやき分」や「1えんぴつ分」など、勝手に単位を作る
- いろんなものの長さ・重さを自作単位で測ってみる
- 普通の単位(cm、g)でも比べてみよう
● まとめ方のコツ
- オリジナル単位一覧表を作るとおもしろい!
- 「この単位はこの測り方に便利」など理由も書くとGOOD
- 写真つきで紹介すると、読んでもらいやすくなるよ
3. 方言クイズをつくってみよう!
● 準備するもの
ノート、家族や親戚へのインタビュー、録音アプリ(あれば)
● やり方
- 家族やおじいちゃん・おばあちゃんに方言を聞いてみる
- 意味や使い方をメモし、方言クイズを作ってみよう
- 学校で出して、友達がどれだけ分かるか試してみる
● まとめ方のコツ
- 方言・意味・使い方の表を作ると見やすい
- 正解率を円グラフにするのもおもしろい
- 方言の「地図」や「年代別の使い方」などに発展しても◎
4. 10円玉をピカピカにして模様をつける
● 準備するもの
古い10円玉、酢、塩、綿棒、小皿、手袋、キッチンペーパー
● やり方
- 酢と塩を混ぜた液に10円玉を入れる
- 綿棒でこすってピカピカに!
- テープなどで型を作って、アート風に模様をつけてもOK
● まとめ方のコツ
- Before / After の写真を並べよう
- 酸化・還元の簡単なしくみを調べて入れるとレベルアップ!
- 一番ピカピカにできた方法を発表しよう
5. 声の大きさで風船はふくらむのか?
● 準備するもの
風船、スマホの音量測定アプリ、録音機、定規、メモ帳
● やり方
- 風船の口を軽く結んで、声をあててふくらむか試す
- 声の大きさ(音の強さ)を変えて比較
- 動いたか・ふくらんだかを記録する
● まとめ方のコツ
- 声の大きさと風船のふくらみを図で見せよう
- 音と空気の関係をかんたんに調べて解説すると◎
- 「予想とちがった!」という気づきを入れると味が出る
実験が楽しくなる!観察&発見がいっぱいの科学ネタ【5選】
6. いろんな紙で“水の吸い上げ”をくらべてみた
● 準備するもの
コップ、水、色水、キッチンペーパー、新聞紙、ティッシュ、トイレットペーパーなど
● やり方
- それぞれの紙を細く切り、水の入ったコップに垂らしてセット
- 水がどこまで吸い上がるかを5〜10分ごとに観察
- 色水だと見えやすくておすすめ!
● まとめ方のコツ
- 吸い上がった長さを測って表やグラフにすると分かりやすい
- 「なぜこの紙が強いのか?」を予想・考察に入れると◎
- 写真を並べて、紙の種類ごとの違いを見せよう
7. 身近なものは電気を通す?通さない?
● 準備するもの
豆電球、乾電池、導線、アルミホイル、えんぴつ、ゴム、プラスチック、スプーンなど
● やり方
- 電池と電球で簡単な回路を作り、間にいろんな素材を挟んでチェック
- 電球が光ったら「通電」、光らなければ「通らない」と記録
- いろんな素材で試して、結果を一覧にする
● まとめ方のコツ
- 「素材」「通ったか」「光の強さ」などを表にして比べる
- 結果から「共通点」を見つけて、自分なりのまとめに!
- 回路の仕組みをイラストで簡単に説明してみよう
8. 音の大きさと水の波の関係を調べる
● 準備するもの
スマホ、スピーカー、ラップ、水、皿、米粒 or 砂
● やり方
- お皿にラップを張って少し水を入れる
- 上に米粒や砂を乗せて、音楽を流して振動を観察
- 音量を変えて、揺れ方に変化があるかを比べる
● まとめ方のコツ
- 音量ごとに揺れの様子を写真で比べる
- 「音=空気の振動」が目に見えるのを説明できると◎
- 音の高さ(高音・低音)での変化も試すとさらに面白い
9. ジュースでつくる手作りリトマス紙
● 準備するもの
紫キャベツ、キッチンペーパー、包丁、鍋、いろんな飲み物(酢・重曹・スポーツドリンクなど)
● やり方
- 紫キャベツをゆでて色水を作る(※火を使う時は大人と一緒に)
- キッチンペーパーをその液にひたして乾かす=手作りリトマス紙!
- 酸性・アルカリ性のものにリトマス紙をつけて色の変化を見る
● まとめ方のコツ
- 色の変化を写真で見せるとインパクトあり!
- 酸性/アルカリ性のちがいを簡単にまとめておく
- 「一番おどろいた変化は?」など自分の感想を入れよう
10. 自分の“動く影”を1日観察してみた!
● 準備するもの
地面にチョーク or 紙とペン、メジャー、時計
● やり方
- 朝〜昼〜夕方の3回くらい、同じ場所で立って影を測る
- 影の向きや長さを記録
- 日の動きと影の変化を比べる
● まとめ方のコツ
- 影の長さ・向きを図で描くと見やすい
- 「なんでこんなに変わったんだろう?」を自分なりに考えてみよう
- 太陽の動きについて調べたことを簡単にまとめると◎
作ってわかる・遊んで学べる!ワクワク工作アイデア【5選】
11. ストローでつくるタワー!どれが一番強い?
● 準備するもの
ストロー、テープ、重り(消しゴム・本など)、定規、記録用紙
● やり方
- 形を変えて(四角・三角・円柱)ストローのタワーを作る
- 上から重りを少しずつのせて、どこまで耐えられるか調べる
- 形ごとの強さを記録!
● まとめ方のコツ
- タワーの設計図を描くと本格的
- 重りをのせた回数や重さを表にしてまとめよう
- 「なぜこの形が一番強かったのか?」を考察!
12. 紙コップスピーカーをつくって音を聞く
● 準備するもの
紙コップ2つ、磁石、銅線、イヤホンの線、スマホ or 音源
● やり方
- 紙コップに銅線をぐるぐる巻いて固定
- 中心に磁石をつけ、線と音源をつなぐ
- 音を流して、音が聞こえるか確認!
● まとめ方のコツ
- 音が出るしくみを絵で説明しよう
- 音の大きさや変化を感じたら、その理由を考える
- うまくいかなかったときの工夫も大切!
13. 空気砲で的あてチャレンジ!
● 準備するもの
ペットボトル or 牛乳パック、風船、輪ゴム、的になる紙コップなど
● やり方
- 空気砲を作る(風船でフタをするだけでもOK)
- 的を作って並べ、どこまで飛ぶか試す
- 的までの距離や命中数を記録する
● まとめ方のコツ
- 命中率や距離を表にしてランキング形式にすると楽しい
- 空気の力で動く仕組みも調べてみよう
- 的のデザインを工夫して、見た目でも楽しめる!
14. まわる!まわる!色の混ざるコマ作り
● 準備するもの
厚紙、ペン、ハサミ、ストロー or 割りばし、のり
● やり方
- 厚紙に好きな色や模様を描いて丸く切る
- 中心にストローや割りばしをさして回す
- 色が混ざって見えるかを観察!
● まとめ方のコツ
- 色の組み合わせによる見え方を記録しよう
- 「なぜそう見えるのか?」を調べて理科的にまとめる
- コマの形や大きさでも違いが出るかも!
15. 光るスライムって作れるの?
● 準備するもの
スライムの材料(洗濯のり・ホウ砂など)、蓄光パウダー or 蛍光ペンインク、容器、スプーン
● やり方
- 普通のスライムを作る
- 蓄光パウダーや蛍光インクを混ぜて、光るかチェック
- 暗い場所やブラックライトで実験!
● まとめ方のコツ
- 光の種類と光り方を表にまとめよう
- 作り方と注意点をわかりやすく書く
- 見た目の変化を写真で紹介すると効果的!
忙しくても安心!10分でできるお手軽自由研究【5選】
16. 牛乳アートで“動く色”を観察!
● 準備するもの
牛乳、食紅(または絵の具)、台所用洗剤、皿、綿棒
● やり方
- 皿に牛乳を注ぎ、数色の食紅をたらす
- 洗剤をつけた綿棒をそっとタッチ!
- 色がパッと広がる様子を観察しよう
● まとめ方のコツ
- 写真で「色の変化」を記録すると伝わりやすい
- 洗剤がなぜ色を動かすのか、表面張力を調べて簡単に説明しよう
- 色の組み合わせをいくつか試して比較してもOK!
17. 食塩水の濃さで卵はどう浮く?
● 準備するもの
水、食塩、卵、コップ、スプーン、計量カップ、記録ノート
● やり方
- 食塩の量を変えた水を数種類作る
- 卵を入れて、どの食塩水で浮くかを観察
- 濃さと浮き方の関係を記録する
● まとめ方のコツ
- 食塩水の濃度ごとに「沈む・浮く・半分浮く」などを書き出す
- 濃度をグラフにして、浮力との関係を説明すると理科っぽくなる!
- 「なぜ浮くのか?」密度や浮力をかんたんに解説
18. “えんぴつの芯”で電気は通るのか?
● 準備するもの
電池、豆電球、導線、えんぴつの芯(B~2Bが最適)、洗濯ばさみなど
● やり方
- 電池と電球を導線でつないで簡単な回路を作る
- 芯を間に挟んで、電気が通るか確認
- 通った場合の明るさもチェック!
● まとめ方のコツ
- 芯の濃さ・太さを変えて実験すると比較できてGOOD
- 「なぜ鉛筆の芯で電気が通るの?」を調べて説明しよう
- 失敗しても、「なぜうまくいかなかったか」を書くと評価UP!
19. 紙飛行機をいろんな形で飛ばしてみた!
● 準備するもの
A4用紙(数枚)、メジャー、ストップウォッチ、ノート
● やり方
- 折り方を変えた紙飛行機を3種類以上作る
- 同じ場所・条件で飛ばし、飛距離・時間を測定
- 結果を平均化して記録
● まとめ方のコツ
- 飛行機ごとの折り方と飛んだ距離を表にまとめる
- 「なぜこの形がよく飛んだ?」を自分なりに考える
- 写真をつけて折り方を紹介してもOK!
20. 消しゴムスタンプでマークを作ってみた!
● 準備するもの
消しゴム、カッター、鉛筆、スタンプインク or 絵の具、紙
● やり方
- 消しゴムに好きな絵を描いて、カッターで彫る
- 絵の具やインクをつけて紙に押す
- 複数のスタンプを組み合わせて作品にしてもOK!
● まとめ方のコツ
- 完成作品を写真で記録しよう
- うまく押せなかった部分も工夫した点として紹介
- 自由研究の表紙や見出しに使って活用しても◎!
以上、人とかぶらない自由研究ネタを5年生向けに20個ご紹介しました!
気になるテーマは見つかりましたか?
自分のアイデアや工夫をプラスして、“世界にひとつだけの自由研究”を楽しんでくださいね。
また、「もっとサクッとできる学習ネタがほしい!」という人には、
➡ 小学5年生のための簡単10分自学アイディア23選とそのまとめ方を紹介 もおすすめです。
毎日の自主学習や宿題にも使える、かんたんで面白いテーマがそろっています!
まわりと差がつく!自由研究を“自分だけの作品”にする3つのコツ
せっかくテーマが決まっても、「なんとなくまとめて終わり…」じゃもったいない!
同じような内容でも、ちょっとした工夫で「これすごいね!」と言われる自由研究になります。
ここでは、まわりと差がつく“まとめ方・見せ方・考え方”のコツを3つにしぼって紹介します。
あなたの自由研究を“自分だけの作品”に仕上げるヒント、ぜひ参考にしてみてください!
コツ①:まとめ方を工夫して“見せ方”で魅せよう!
- 写真やイラストをたくさん使って、見た目を楽しく!
- 手書きの研究ノート風/新聞風など、見せ方を変えると目立つ!
- 表やグラフを使って、わかりやすく伝えよう!
コツ②:ちょっと比較するだけで研究っぽさがアップ!
- 同じ実験でも条件を変えてくらべると、より本格的な研究になる!
- 結果がちがったら、その理由を「自分の言葉」で考えてみよう!
- ランキングや比較表にすれば、まとめやすくなるよ!
コツ③:自分の「気づき」や「感想」がいちばんのオリジナリティ!
- 「やってみてびっくりしたこと」「うまくいかなかったこと」も大事な研究!
- 「次はこうしてみたい」「もっと知りたくなった!」を入れると◎
- 自分の言葉でまとめれば、“かぶらない”研究に仕上がる!
まとめ|自由研究は「やり方」より「じぶんらしさ」がカギ!
自由研究は、「どんなテーマにするか」だけじゃなく、どんなふうにまとめるか、どう工夫するかもとっても大切。
今回紹介した20のアイデアは、5年生でも楽しく取り組めて、人とかぶらない研究になるヒントがたっぷり詰まっています。
やりたいテーマが見つかったら、
- ちょっと見せ方を変えてみる
- 比べてみる
- 自分の気づきをしっかり書いてみる
そんな小さな工夫をプラスして、“自分だけの自由研究”を作ってみてくださいね!
5年生におすすめの関連記事
➡ 他学年のユニークな自由研究ネタも参考にしたい方へ
【小学生向け】人とかぶらない自由研究 1年生〜6年生まで学年別アイデア80選
➡ 10分でできる簡単な自学ネタを探している方へ
【小学5年生のための簡単10分自学アイディア23選とそのまとめ方を紹介】
➡ 毎日の学習にも役立つ!全学年対応のまとめ記事
【小学生の自主学習ネタ192選!学年別にすぐ使えるアイデアとコツを紹介】