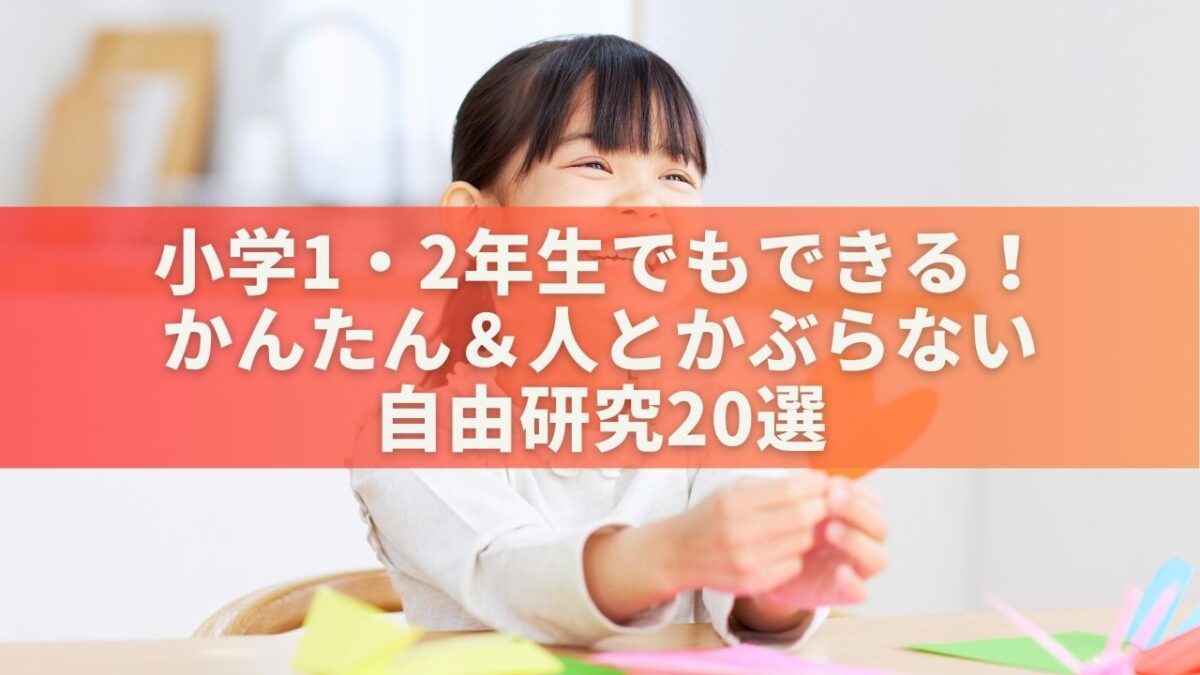「自由研究って、なにをやればいいの?」「まだ1年生だけど、大丈夫かな…?」
そんな小学校1・2年生のお子さんや保護者の方に向けて、かんたんで楽しく取り組める自由研究アイデアを20個まとめました!
実験・観察・工作など、女の子にも男の子にも人気のテーマをたくさん紹介しています。
夏休みの課題として「人とかぶらないものがいい」「1年生でもできるものを探したい」という方にもぴったり。
親子で楽しめて、完成したあとも思い出に残るような自由研究を見つけてくださいね!
小学1・2年生でもできる!人とかぶらない自由研究20選
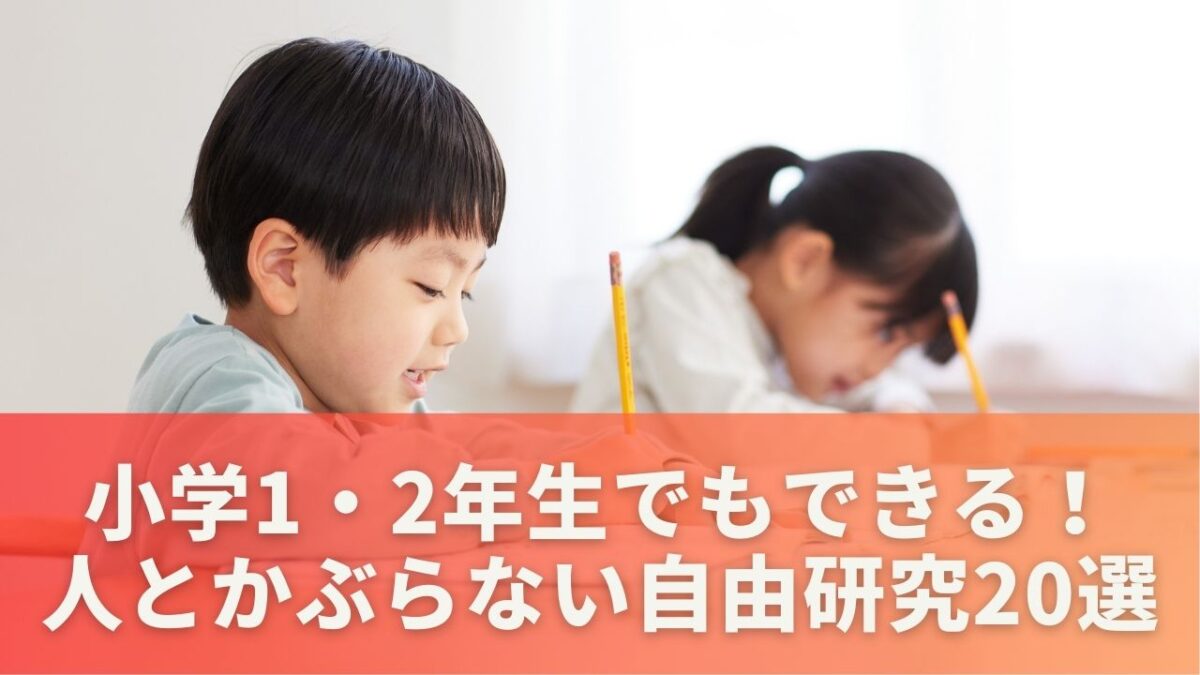
むずかしいことをしなくても、かんたんな工夫や発想だけで“人とかぶらない”自由研究はつくれます。
ここでは、1・2年生でも無理なく楽しめるアイデアをジャンル別に20こご紹介します!
やってみたくなる!ふしぎでたのしい自由研究アイデア【5選】
1. 牛乳アートで色がうごく!? ふしぎなえをかこう
● 用意するもの
牛乳/お皿/食紅(または水にとかした絵の具)/食器用洗剤/綿棒
● やり方
- お皿に牛乳を少し入れます
- 食紅を2~3滴たらします(色は何色でもOK)
- 洗剤をつけた綿棒をそっとタッチすると…色がひろがります!
● まとめ方のコツ
- 模様の変化を写真に撮って、色の動きを観察してみましょう
- どんな色ができたか、子どもと一緒に「絵」としてまとめるのもおすすめです
- 「どうして動いたのかな?」という子どもの気づきを自由に書かせると◎
2. にんじんの葉っぱはのびる?野菜のかんさつ
● 用意するもの
にんじんのヘタ(葉の部分を少し残す)/小さなお皿/水/カップ/日光のあたる場所
● やり方
- にんじんのヘタを少し水を入れたお皿に置きます
- 毎日決まった時間に観察し、葉が伸びてくる様子を記録します
- 数日〜1週間程度で変化がわかります
● まとめ方のコツ
- 毎日の変化を写真やスケッチで残しましょう
- 葉っぱの長さや色の変化を記録してグラフ化しても◎
- 「気づいたこと」「どうしてこうなると思う?」を親子で話して書き出してみてください
3. くつしたロケットをとばしてみよう!
● 用意するもの
長いくつ下/風船(できれば大きめ)/テープ/ストロー
● やり方
- ストローに風船をつけて、くつ下でカバーします
- 息を入れてふくらませたあと、手を離すとビューン!
- 飛ぶ向き・長さを観察して記録します
● まとめ方のコツ
- 何回かとばして、飛ぶ距離をくらべてみましょう
- 写真つきで「ロケットのしくみ」を見せると◎
- くつ下を変えたらどうなる?など発展もできます
4. おとで水がゆれる?ふしぎな音のじっけん
● 用意するもの
浅いお皿/水/ラップ/ゴム(または輪ゴム)/米粒/スマホやスピーカー
● やり方
- お皿に水を入れ、ラップをピンとはって米粒をのせます
- スピーカーやスマホを近づけて、音をならします
- 音量や音の種類でゆれ方がちがうかを観察
● まとめ方のコツ
- 音の大きさや高さでのゆれ方のちがいを絵や写真でまとめましょう
- 「びっくりしたこと」「もっとやってみたいこと」も子どもに書かせてみてください
- なぜゆれたのか?を保護者が補足で入れてもOK
5. いろんなたねをあつめて、くらべてみよう!
● 用意するもの
スイカ・パプリカ・トマト・ピーマンなどの種(料理で出たものでOK)/ノート/カップなど保存容器
● やり方
- 家で出た野菜やくだものの種をあつめて、種類別に分けます
- 色・形・大きさ・数などを観察して記録します
- 好きな種を絵に描いても楽しい!
● まとめ方のコツ
- 観察結果を表や絵にしてまとめると見やすくなります
- 「この種はまるい」「この種はたくさんあった」など自由に書かせるとOK
- 「どんな花が咲くのかな?」と育ててみるのもおすすめ!
かんたんにできる!びっくり実験テーマ【5選】
6. 氷はどこが一番早くとける?おへやじっけん
● 用意するもの
氷/皿/テーブル/タイマー/お湯(水)/あついおふろ(やけどに注意)
● やり方
- 皿に氷をいくつかおいて、温かいお湯や空気をあててみる
- どこが一番早く溶けるか、時間を測って記録
- お部屋の中や外において、あたたかい・冷たい場所で比べてみよう
● まとめ方のコツ
- 溶けるスピードをグラフにしてまとめると見やすくなります
- 溶ける速さのちがいを、「どうしてこうなったのかな?」と考えてみる
- 写真をつけて、結果の「ビフォー・アフター」を見せると良い!
7. 風船でうごく!かんたんボートづくり
● 用意するもの
風船/ストロー/輪ゴム/ペットボトル/テープ/水
● やり方
- ペットボトルにストローをつけ、風船を膨らませてつけます
- 水をはったお皿に浮かべ、風船を膨らませるとボートが進みます
- どこまで進むか、何回も試してみよう
● まとめ方のコツ
- 風船の大きさや進んだ距離を表にして比べよう
- どんな風に進んだのか、子どもが感じたことをかんたんにまとめる
- 観察して「どうして進んだのか?」をみんなで考えてみよう!
8. 水にとける?とけない?たしかめじっけん
● 用意するもの
コップ/水/いろんなもの(砂糖、塩、油、粉など)
● やり方
- いろんなものを水にいれて、どれがとけるか、どれがとけないか観察
- 何がとけるか、どれがとけないかを調べて記録
- お水の中で、どれが一番とけるか比べてみよう!
● まとめ方のコツ
- どれがとけたのか、見た目や時間を表でまとめてみよう
- 「とける理由」「とけない理由」を簡単に説明してあげると分かりやすい
- かんたんな図を使って、結果を見せるともっとわかりやすい!
9. 10円玉をピカピカにしてみよう!
● 用意するもの
古い10円玉/酢/塩/コップ/スプーン
● やり方
- 10円玉を酢と塩の液に入れて、どれくらいきれいになるか観察
- 10円玉をおいておく時間や方法で、きれいになる速さを比べてみよう
- どの方法が一番ピカピカにできるか調べて、写真に残そう
● まとめ方のコツ
- きれいになった時間や方法を表にして比べてみよう
- 「どうしてピカピカになったのかな?」と子どもと話しながらまとめる
- 結果をイラストや写真で見せると、さらにわかりやすい!
10. 紙のはしで水をはこべる!? 水のぼりじっけん
● 用意するもの
紙/コップ/水/ストロー/お皿
● やり方
- 紙をいろんな形に切って、ストローで水を吸わせてみる
- 水がうまくはこべるか、いろいろなやり方を試してみよう
- どの形が一番うまく水を運べるかを比べてみよう
● まとめ方のコツ
- うまく水がはこべた形や、うまくいかなかった形を比べる
- 写真や絵を使って、どんな形にしたかを見せると良い
- 水が運べるしくみをやさしく説明してあげると、さらに楽しい!
工作が好きな子に!作ってあそべる自由研究【5選】
11. ストローでクルクルかいてん工作!
● 用意するもの
ストロー/画用紙(丸く切ったもの)/はさみ/のり/ペン/つまようじ or 割りばし
● やり方
- 画用紙を丸く切り、色や模様をかきます
- 中心に穴をあけて、つまようじやストローを通します
- 手で回して、色のまざり方や模様の変化を見てみましょう!
● まとめ方のコツ
- どんな色を使ったらどう見えたか、絵や写真で見せよう
- 回すはやさや角度を変えてくらべてみても◎
- 「ふしぎに見えたところ」や「工夫したところ」を自分の言葉で書いてみよう!
12. にじいろおりがみで光あそび!
● 用意するもの
トレーシングペーパー(または半透明の包装紙)/油性ペン/はさみ/のり/画用紙/窓
● やり方
- トレーシングペーパーに色をぬって模様をつくる
- 画用紙のフレームに貼ってステンドグラス風に仕上げる
- 窓にかざして光を通して見てみよう!
● まとめ方のコツ
- どんな色の組み合わせがきれいだったか絵で見せよう
- 朝・昼・夕方での見え方のちがいをくらべてもOK
- 「こうするともっときれいになる!」など自分の工夫を書くと◎
13. 手作りゆらゆらバランスおもちゃ
● 用意するもの
牛乳パック or 厚紙/ペン/おもり(10円玉・ビー玉など)/はさみ/テープ
● やり方
- 好きな形のキャラクターなどを作る
- 下のほうにおもりをテープでつけてバランスをとります
- 机のはしなどに置いて、ゆらゆら動かしてみましょう
● まとめ方のコツ
- おもりの位置や重さを変えて、どんなふうにゆれ方が変わるか観察
- いろいろ作って「どれが一番安定したか」などをまとめてもOK
- 工作のポイントや作るときのコツをわかりやすく書いてみよう!
14. 水でうごくくるまをつくろう!
● 用意するもの
ペットボトル or 牛乳パック/キャップ/ストロー/竹串/ペットボトルのフタ(タイヤ用)/テープ
● やり方
- 牛乳パックを車のボディにして、ストローと竹串でタイヤを取りつけます
- ストローから水を押し出すしくみで、車が前に進むかを試します
- どれだけ進むか観察してみましょう
● まとめ方のコツ
- 写真や絵で作り方と進むようすを記録
- 「まっすぐ走った?」「うまくいかなかったときは?」を自分の言葉で書こう
- 距離をはかってグラフにしてもOK!
15. 紙コップのジャンピングおもちゃ!
● 用意するもの
紙コップ2つ/輪ゴム/カッター(※保護者と一緒に)/テープ/飾りつけようの色紙など
● やり方
- 紙コップに切れこみを入れて輪ゴムを引っかけます(ジャンプのバネになります)
- もう1つの紙コップを下にして、上からはめ込むようにセット
- 手を離すとピョーンとジャンプ!
● まとめ方のコツ
- どれくらいジャンプしたかを距離や高さで比べてみましょう
- ゴムの本数を変えてくらべると研究らしさが出ます
- ジャンプしたときの写真や感想も入れて楽しくまとめてみよう!
忙しい日でも安心!10分でできるお手軽ネタ【5選】
16. シャボン玉はどこまで大きくなる?
● 用意するもの
シャボン液(市販 or 水+洗剤+少量の砂糖)/ストローやうちわのフレーム/外(風の少ない場所)
● やり方
- いろんな道具でシャボン玉をつくります
- どの道具で一番大きくなるかを試してみましょう
- 大きさやすぐ割れたかなどを記録します
● まとめ方のコツ
- 写真で大きさのちがいを見せると楽しい!
- どの道具がよかったかを表にしても◎
- 「もっとこんな道具も試したい!」と書くと発展になります
17. おかしのふくろでマラカスづくり!
● 用意するもの
おかしの空袋/お米・豆・小石など音が出るもの/テープ/ペン
● やり方
- 袋の中に材料を入れて、テープでしっかりとじます
- ペンでデコレーションして、オリジナルマラカスを完成させよう
- 振ったときの音をきいてくらべてみます
● まとめ方のコツ
- 音のちがいを文字や絵で表現してみよう
- どの材料が一番大きな音?どんな音?と感想を入れると◎
- 「ふる強さ」や「袋の大きさ」など条件を変えても楽しいです
18. 色がかわるジュース?くだものじっけん
● 用意するもの
紫キャベツ/お湯/透明カップ/レモン汁・重曹水・ジュースなど数種類
● やり方
- 紫キャベツをゆでて、できた紫の液を使います
- 各ジュースにキャベツの汁を入れて、色がどう変わるか観察します
- 酸っぱいもの、あまいものなどで色が変化!
● まとめ方のコツ
- 「どんな色に変わったか」を表にして見せよう
- どの飲みものがいちばん変わった?をグラフにしても◎
- なぜ色が変わったかを調べて簡単に書いてもOK!
19. かげのながさをくらべてみよう
● 用意するもの
ペットボトル or 人形/はかるもの(メジャーや定規)/太陽が出ている日
● やり方
- 同じ場所で朝・昼・夕方にかげを見て、長さを記録します
- 足元にチョークなどでしるしをつけても◎
- 向きのちがいも観察しましょう
● まとめ方のコツ
- 時間と長さの変化をグラフにすると見やすいです
- 太陽の動きと関係があることに気づけたらすばらしい!
- 「びっくりしたこと」「もっとやってみたいこと」も自由に書いてOK
20. おうちの中で「まる」さがし大さくせん!
● 用意するもの
ノート/ペン/家の中(キッチン・おふろ・リビングなど)
● やり方
- 「まるいかたちのもの」を家の中でさがして記録します
- どこに多かったか?何に使うものだったか?を書いていきます
- おなじ形でも大きさ・色・使い方などをくらべてみましょう
● まとめ方のコツ
- さがした場所ごとに表をつくるとわかりやすい
- 「どんなまるがいちばん多かった?」など、自分なりのまとめも入れましょう
- 写真やスケッチを入れるとより見やすくなります!
自由研究がもっと楽しくなる!“まとめ方”のアイデア集
1・2年生の自由研究は、“たくさん書く”より、“わかりやすく見せる”ことが大切。
特に1年生の場合は、絵や写真を使ったまとめ方にすると、女の子・男の子問わず楽しく続けやすいです。
絵や写真でまとめて、わかりやすく伝えよう
- 自分で描いた絵やスケッチ、作った工作の写真などを使って、研究のようすを伝えよう
- 「じっけんの前と後」「工作しているときのようす」など、見たままをまとめるだけでOK!
- おうちの人と一緒に撮った写真をのせるのもおすすめです
「くらべてみる」で研究っぽさがアップ!
- 材料ややり方を少しずつ変えてくらべると、研究っぽさがアップ
- ○×マークや色分けなど、子どもでもわかりやすいかたちでまとめてみましょう
- グラフや表にすることで、1年生でも立派な自由研究に!
感想はふきだしや一言メモでじぶんらしさを
- 「びっくりした!」「楽しかった!」という言葉を大事に
- 手書きのふきだしやメモカードで自由に書くと、その子らしい研究になります
- 工作が好きな子は、感想を飾りつけしてアルバム風にしても◎
タイトルや見出しも、自分だけのオリジナルで!
- 「色がかわるふしぎじっけん」「わたしだけのこうさくマラカス」など、女の子・男の子それぞれの“好き”が出るネーミングもポイント!
- 楽しかった気持ちをこめて、自分だけの自由研究タイトルを考えてみよう
このまとめ方なら、1年生でも楽しみながら「自分でできた!」を実感できるはずです。
工作が好きな子も、実験やかんさつが好きな子も、“じぶんらしいまとめ方”でかぶらない自由研究にチャレンジしてみてください!
まとめ|かんたんでも“じぶんらしい”自由研究がいちばん!
1・2年生にとっての自由研究は、「むずかしいこと」よりも、楽しく・わかりやすく・自分でできた!という体験が何より大切です。
この記事で紹介した20のテーマは、どれも男の子も女の子も取り組みやすいアイデアばかり。
とくに1年生には、簡単にできる工作や観察からスタートするのがおすすめです。
「人とかぶらない研究」にするためには、やり方を少し工夫したり、まとめ方に自分らしさを出すことがポイント。
ぜひ、お子さんと一緒に自由研究を楽しみながら、“じぶんだけの作品”を完成させてみてくださいね!
お兄ちゃん・お姉ちゃんはどんな自由研究をしてるのかな?
他の学年の自由研究アイデアもまとめてチェックしたい方はこちら!
➡ 【小学生向け】人とかぶらない自由研究 1年生〜6年生まで学年別アイデア80選
学年別の自主学習ネタを探したい方はこちらの記事をどうぞ。