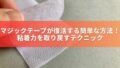長距離の移動が多い新幹線では、トイレの位置が気になりますよね。
この記事では新幹線のトイレが近い席や、子連れの方に便利な車両の情報もお届けします。
また、便利なトイレマークランプについてもご紹介。
これは座席からトイレの使用状況が一目で分かるとても便利な機能です。
新幹線旅の際はぜひ活用してみてくださいね。
新幹線のトイレ位置は奇数号車!旅行前にチェック

新幹線での長距離移動や子連れの旅行の際、トイレの位置を事前に知っておくと安心♪
特に座席選びには重要な情報になります。
実は、新幹線のトイレは主に奇数号車に設置されているのが一般的です。
つまり、1号車、3号車、5号車など、奇数の号車にトイレが配置されていることが多いのです。
例えば、1号車のトイレは2号車の近くの端に配置され、他の奇数号車も同じように設計されています。
この情報を頭に入れておけば、トイレへのアクセスがしやすい座席の選択が可能になりますね。
特に長時間の移動や小さなお子様連れの場合は、トイレの近くの席を選ぶと便利ですよ。
N700系新幹線のトイレの配置
N700系新幹線は、東海道、山陽、九州の各区間を結ぶ新幹線です。
この新幹線には「のぞみ」、「ひかり」、「こだま」という愛称があります。
これらの列車は16両編成で運行されており、トイレの配置はどの列車も同じです。
具体的には以下のとおりです。
- 1号車、3号車、5号車、7号車、9号車、11号車、13号車、15号車にトイレが設置
- 男女兼用のトイレが2つと男性用トイレが1つ設置
- 3号車、7号車、10号車、15号車には喫煙ルームが設置
- 11号車には多目的室と多目的トイレが設置
山陽新幹線を走る一部の「ひかり」と「こだま」では、8両編成の列車もありますが、こちらにも同様に奇数号車(1、3、5、7、9号車)にトイレがあります。
11号車には多目的室と多目的トイレがあるため、子連れや大きな荷物を持つ方にとって便利な選択肢となりますね。
多目的室は通常施錠されており、利用を希望する場合は車掌や乗務員に声をかける必要があります。
多目的室は身体の不自由な方の利用が優先され、障害者手帳の提示が必要な場合もありますが、空いていれば授乳や着替え、体調不良時にも追加料金なしで利用可能ですよ。
E5系新幹線のトイレの配置
E5系新幹線は東北や北海道区間を走る新幹線で、「はやぶさ」、「はやて」、「やまびこ」、「なすの」という愛称で親しまれています。
この新幹線は1号車から10号車までの構成で、女性専用のトイレや広々とした洗面所が設置されており、長時間の移動中でも快適に過ごせる工夫がされています。
- 1、3、5、7、9号車にトイレ設置
- 1、3、7号車には男女兼用、男性用、女性用の3種類のトイレがある
- 5、9号車には車椅子対応のトイレ設置
5号車には多目的室があり、小さなお子様連れの方には便利な設備です。
トイレのある車両にはベビーベッドも設置されており、子供との旅行時には奇数号車が特におすすめです。
ベビーベッドの存在は、飲み物をこぼした際の着替えや休憩にも便利で、子供との旅行でも安心ですね。
E6系新幹線のトイレの配置
E6系は、東北地方や秋田を結ぶ新幹線で、「こまち」、「はやぶさ」、「やまびこ」、「なすの」といった愛称で知られています。
この新幹線は11号車から17号車までの7両編成で運行され、そのトイレの配置は一般的な奇数号車に限定されていません。
E6系新幹線の特徴は以下の通りです。
- トイレは12号車、13号車、14号車、16号車に設置。
- 各車両に男女兼用トイレと男性用トイレが設けられています。
- 特に12号車には多目的室があり、より快適な利用が可能。
- トイレ設置車両にはベビーベッドも搭載されており、小さなお子様連れの方にも安心。
このようにE6系新幹線は、利便性を考慮した設備で乗客に快適な旅行体験を提供しています。
新幹線各路線における多目的トイレの位置
新幹線での移動中、多目的トイレを探す際は、各路線によってその位置が異なることを知っておくと便利です。
特に車椅子対応の座席がある車両に設置されている点に注意が必要です。
東海道新幹線の「のぞみ」「ひかり」「こだま」では、16両編成の列車においては11号車に多目的トイレが設けられています。
山陽新幹線では、16両編成の「のぞみ」と「ひかり」も同様に11号車に設置されていますが、8両編成の「ひかり」(レールスターを含む)、および「こだま」「みずほ」「さくら」では7号車に多目的トイレがあります。
北陸新幹線の場合、「かがやき」「はくたか」「つるぎ」の列車では、7号車または11号車に多目的トイレが設置されています。
これらの情報を把握しておくと、新幹線での移動がより快適になるでしょう。
新幹線のトイレランプの役割と使い方

新幹線では、トイレの使用状況を簡単に知ることができるようになっています。
各車両にある電光掲示板近くのトイレマークランプを確認することで、トイレが使用中かどうかを判断できます。
このトイレマークランプが点灯しているときは、そのトイレが使用中であることを意味しています。
トイレを使う際は、このランプの点灯状況を確認することが大切です。
このシステムは、席を立たずにトイレの使用状況が分かるため、非常に便利です。
ランプはトイレ個室の鍵と連動しており、鍵が閉まると点灯する仕組みになっています。
トイレマークの位置は多少異なるものの、ランプが点灯しているという合図は全車両で共通です。
しかし、新幹線が混雑している時やトイレ前に待ち行列ができている場合、ランプだけを頼りにしていてもすぐに入れないことがあります。
そのため、トイレを急いで利用したい時は、直接トイレ前に行く方が効率的です。
また、男性用の小便器には鍵がないため、使用中であってもランプは点灯しません。
男性が小便器を使用する際は、特に注意が必要です。
新幹線の多目的トイレでの授乳とオムツ交換

新幹線に備えられている多目的トイレは、もともとは身体障害者や車椅子利用者のための設備ですが、他の乗客も利用することができます。
特に、乳幼児を連れた親御さんにとって重宝しますよね。
便器に座って授乳を行うことが可能であり、トイレ内には赤ちゃんのオムツ交換台も設置されています。
これにより、赤ちゃんのおむつ交換を新幹線の移動中にも安心して行うことが可能ですよ。
新幹線の車内には、トイレ以外にも快適に過ごすための機能がいくつか備わっています。
たとえば「車内でスマホを使いたい」と考える方にとって、Wi-Fiの接続状況も気になるポイント。
こちらの記事では、実際につながらない原因や、スムーズに接続するための方法を詳しく解説しています。
➡ 新幹線でWi-Fiが繋がらない!接続トラブルの原因と解決策を紹介
乗車前にチェックしておくと、移動中のイライラを減らせますよ。
新幹線でトイレを利用する際の荷物の扱い方3つの方法

新幹線に乗車している時、トイレに行く必要がある場合、荷物の扱いに困ることがあります。
特に一人旅や出張時には、荷物の管理に注意が必要です。
そこで、安心してトイレに行ける3つの荷物管理方法を紹介します。
- 貴重品のみを持ち歩く
- 隣の席の乗客に見守ってもらう
- 荷物を持って行く
これらの方法を使えば、新幹線でのトイレ利用時も荷物の安全を確保しつつ、安心して用を足すことができます。
1つずつ詳しく説明しますね。
新幹線内での荷物管理:貴重品のみを持ち歩く
新幹線でトイレに行く際、貴重品のみを持ち歩く方法がおすすめです。
財布や携帯電話など、小さな貴重品を小バッグに入れて持っていくことで、トイレの荷物掛けに掛けることができ、安心ですね。
この方法のメリットは、貴重品の管理が自分で可能な点と、身軽さを保ちつつ安心できるバランスが取れていること。
新幹線の車内通路や通常のトイレのスペースは限られているため、大きな荷物を持ち歩くのは避けた方が無難です。
特に旅行用のキャリーケースなどは、揺れる車内で扱うのは危険ですし、トイレに持ち込むのも難しいでしょう。
そのため、大きな荷物は座席の隅にまとめて置き、上着などをかぶせておくと良いでしょう。
これにより、走行中の揺れで荷物が動いてしまうのも防げます。
安心してトイレに行くための小さな工夫ですが、快適な旅行には大切なポイントですね。
新幹線内での荷物管理:隣の人に荷物を見てもらう
新幹線でトイレに行きたくなった時、一番手軽な方法は隣の人に荷物を見てもらうことです。
これはちょっと勇気がいるかもしれませんが、トイレに行く短い間、隣の人に荷物の監視を頼むと身軽に動けます。
一人で座席を取る場合、隣に誰かが座る可能性は高いです。
トイレに行きたいとき、隣に人がいれば、勇気を出して「荷物を見ていてもらえますか?」とお願いしてみましょう。
多くの場合、人は快くこのお願いを引き受けてくれます。
ただし、この方法にはトラブルのリスクもあります。
完全な見ず知らずの人に頼むのは不安かもしれません。
最終的には自分の直感や状況に応じて、この方法を選ぶか、他の方法を選ぶかを判断することが大切です。
新幹線内での荷物管理:全ての荷物を持って行く
新幹線でトイレに行く際、特に荷物が少ないか、重要な物品ばかりの場合は、全ての荷物を持って行くのが一つの方法です。
これにより、盗難や破損のリスクを最小限に抑えることができます。
しかし荷物の量によっては、他の乗客に迷惑をかける可能性もあるため、この方法は最終手段として考えましょう。
指定席であれば比較的安心ですが、自由席ではトイレに行っている間に席を取られるリスクがあります。
自由席で席を保持したい場合、目立つアイテムを席に置いておくと良いでしょう。
これにより、「この席には誰かが戻ってくる」というサインを残すことができ、トイレから戻っても同じ席に座れる可能性が高まります。
ただし、新幹線の自由席車両が混雑している場合は、他の乗客との譲り合いを心がけましょう。
状況を見て、トイレから戻った後に元の席に座るのが難しそうなら、あらかじめ荷物を全て持って移動し、同じ席に座ることをあきらめるのがトラブルを避ける最善の方法です。
トイレの位置をあらかじめ確認しておくと、乗車後に慌てずに済みます。
とくに自由席の場合は、早めに並ぶ・座席を確保することが重要です。
➡ 新幹線は何分前から乗れる?始発駅と途中駅でのタイミングの違いを解説
乗車可能時間の目安や、駅ごとの違いを知っておくことで、トイレや座席の場所もゆとりを持って選べます。
まとめ

新幹線を利用する際、トイレの位置を知っておくと便利です。
新幹線では、トイレは主に奇数号車に設置されています。
具体的には1号車、3号車、5号車などの車両です。
特に東海道新幹線の「のぞみ」、「ひかり」、「こだま」などの列車は、これらの奇数号車にトイレが備わっています。
そのため、トイレの近くに座りたい場合は奇数号車を選ぶと良いでしょう。
さらに、車椅子対応の座席がある車両には多目的トイレも設けられています。
トイレの場所や設備を知っておくだけでも、安心して新幹線に乗れるものですが、天候が不安定な時期には、「そもそも列車がちゃんと動くのか?」という心配も出てきますよね。
こちらの記事では、台風や大雨などの影響で新幹線が遅延・運休する可能性があるとき、どう情報をチェックし、どう行動すればよいかを詳しく紹介しています。
➡ 台風で新幹線が止まる基準は?遅延と運休の予測と効果的な対策マニュアル
新幹線を利用するときは、これらの情報を活用し、快適な旅行をお楽しみくださいね。